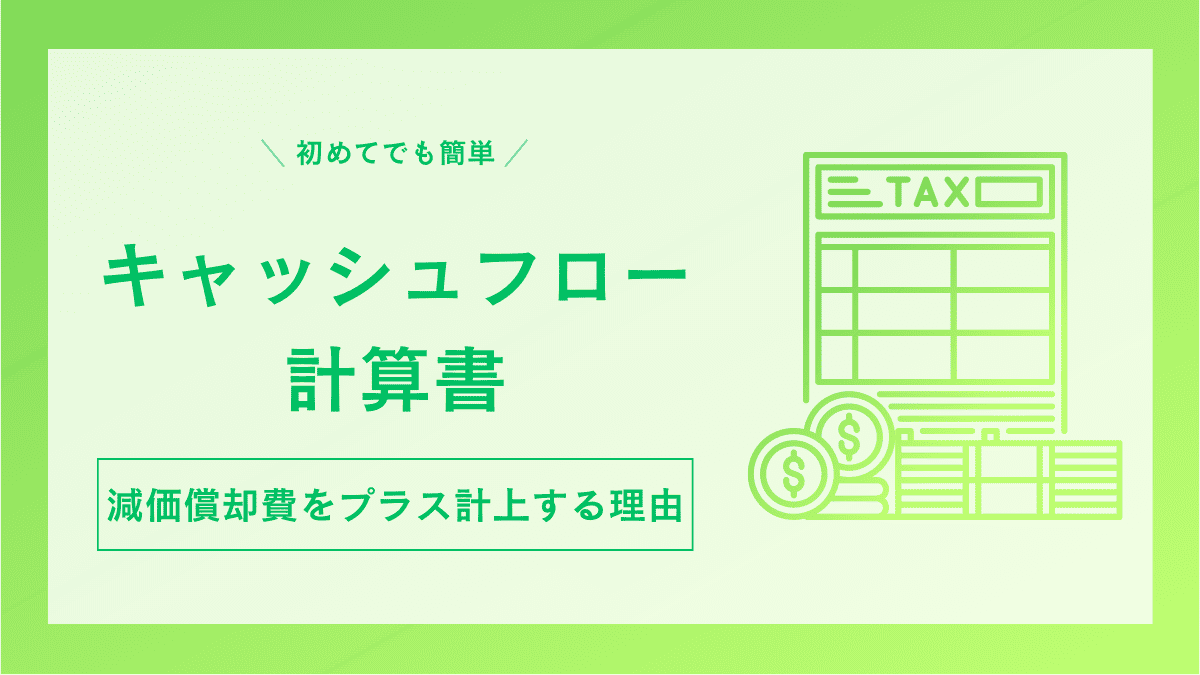「キャッシュフロー計算書で、減価償却費をプラスする理由は何だろう?」とお悩みではありませんか?
減価償却費はキャッシュフロー計算書と損益計算書で扱いが異なるため、理解しづらい人も多いことでしょう。
そこで、本記事ではキャッシュフロー計算書で減価償却費をプラス計上する理由や、減価償却やキャッシュフロー計算書の基本的な内容についても詳しく解説していきます。
さらに、減価償却費以外でキャッシュフロー計算書において調整が必要な項目も解説します。
キャッシュフロー計算書と減価償却費の関係でお悩みの人は、ぜひ最後までお読みください。
キャッシュフロー計算書における減価償却費の扱い方
キャッシュフロー計算書を作成する際は、入ってくるお金(キャッシュイン)と出ていくお金(キャッシュアウト)を把握し、記載していきます。
しかし、減価償却費は損益計算書では費用で計上されるものの、キャッシュが動いたわけではないのです。
したがって、キャッシュフロー計算書では、減価償却費は記載されないものとして扱われます。
もし、キャッシュフロー計算書を間接法で作成する場合、営業活動によるキャッシュフローで減価償却費が加算されるのは、上記の通り減価償却費がキャッシュを伴わないことが理由です。
減価償却とは?
キャッシュフロー計算書での減価償却費の扱いを理解するために、まずは減価償却について詳しく解説していきます。
ここで解説する内容は、下記の3つです。
・設備投資等の費用を一定期間に配分する会計処理
・会計上のルールである「費用収益対応の原則」
・減価償却ができる資産とできない資産
一つずつ解説していきます。
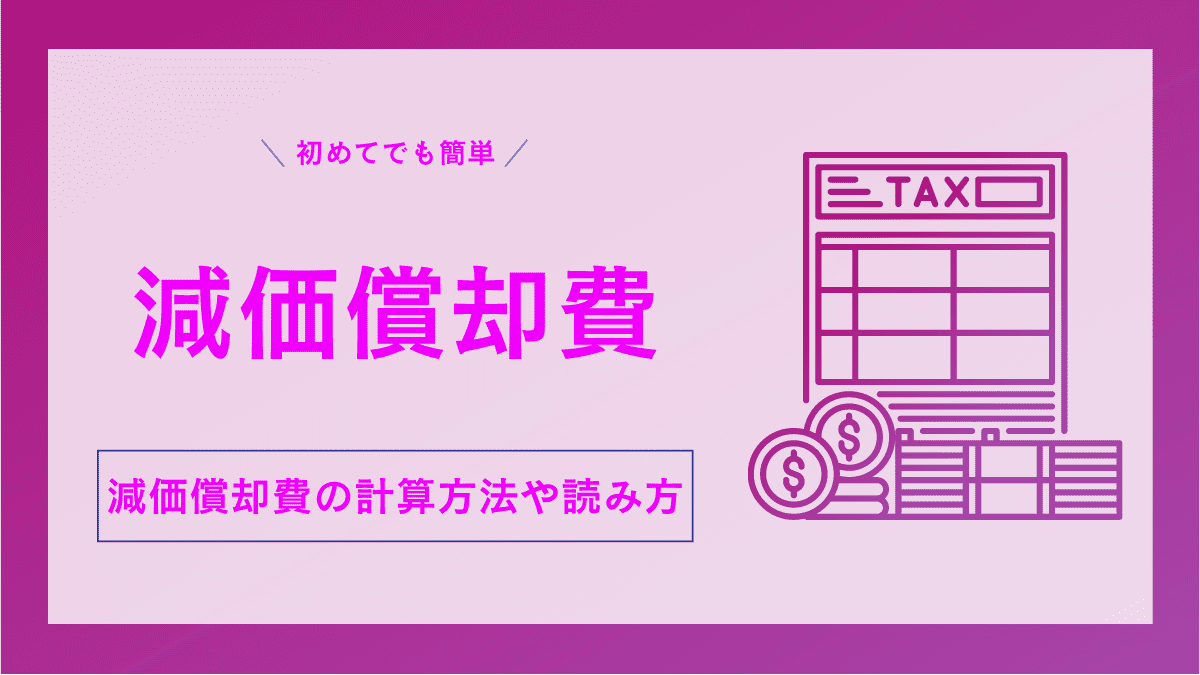
設備投資等の費用を一定期間に配分する会計処理
減価償却とは、設備投資の購入費用を、計上した会計期間で一括で計上するのではなく一定期間に配分する会計処理のことです。
建物や機械装置などの固定資産は税法によって耐用年数が決まっており、それぞれの耐用年数をもとに減価償却費を計上していきます。
また、減価償却費を計算する際には、下記の2つの方法があることも覚えておきましょう。
・定額法:毎年同じ金額を減価償却していく計算方法
・定率法:減価償却を開始した初めの年に多く減価償却費が計上され、年々計上する減価償却費が少なくなる計算方法
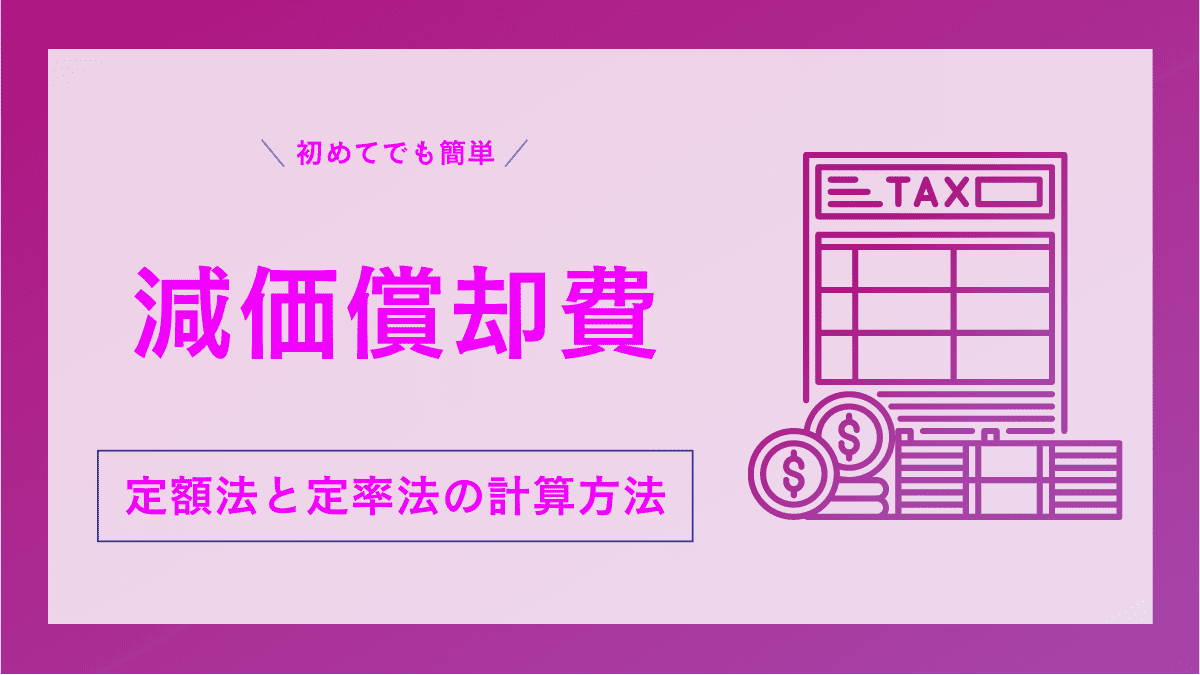
さらに、減価償却費の仕訳についても、下記の2つの方法があることもあわせて覚えておくとよいでしょう。
・直接法:固定資産の帳簿価額から直接減価償却費を減らす方法
・間接法:固定資産の取得時の勘定科目とは別に、減価償却累計額の勘定科目を用いて減価償却費を記帳する方法
会計上のルールである「費用収益対応の原則」
減価償却を行う際、固定資産を取得した会計年度に一括計上せずに、一定期間で配分するのは「費用収益対応の原則」があるからです。
費用収益対応の原則とは、費用と収益を対応させ、当期の損益計算を正しく行うための会計上のルールです。
固定資産は取得した年だけでなく、翌期以降も企業が収益をあげるために使われることが想定されます。
したがって、減価償却費も取得した年だけでなく、固定資産が使われる間に費用を計上することになります。
減価償却ができる資産とできない資産
実は、減価償却ができる資産とできない資産があることをご存じでしょうか?
減価償却ができない代表的な資産は、土地です。
建物であれば時間の経過により劣化しますが、土地は時間が経過しても価値がなくならないことから、減価償却されません。
減価償却ができる資産とできない資産の例は下記の通りですので、確認しておきましょう。
・減価償却ができる資産:建物、機械装置、構築物、車両運搬具など
・減価償却ができない資産:土地、建設仮勘定、美術品、骨董品、ゴルフ会員権など
減価償却費とは?
前の章で減価償却について解説しましたが、ここでは減価償却費について見ていきましょう。
ここで解説するのは、下記の2つです。
・減価償却費は「非現金支出費用」に該当する
・減価償却費と減価償却累計額の違い
1つずつ解説していきます。
減価償却費は「非現金支出費用」に該当する
減価償却費は、費用が計上されても実際に現金が出ていかないため「非現金支出費用」に該当します。
損益計算書で減価償却費が計上されると、利益が減るため法人税は減りますが、キャッシュフロー計算書上では現金が減らないことになります。
上記のように、減価償却費は損益計算書とキャッシュフロー計算書で扱いが異なることが、頭を悩ます原因になっていると考えられるでしょう。
減価償却費と減価償却累計額の違い
似た勘定科目で「減価償却費」と「減価償却累計額」がありますが、違いは何でしょうか?
減価償却費は、当年の会計期間で計上された1年間分の費用で、損益計算書に表示される勘定科目です。
一方、減価償却累計額は、これまでの年度で計上されてきた減価償却費の合計金額を表し、貸借対照表に表示される勘定科目になります。
分かりづらい人は、減価償却費は「1年分の費用で損益計算書に表示」、減価償却累計額は「複数年の費用で貸借対照表に表示」と覚えるとよいでしょう。
キャッシュフロー計算書とは?
ここでは、キャッシュフロー計算書について、下記の3つの項目で解説していきます。
・お金の出入りを表す財務三表のひとつ
・経営状況を把握するための資料
・間接法で作成するのが一般的
一つずつ確認していきましょう。
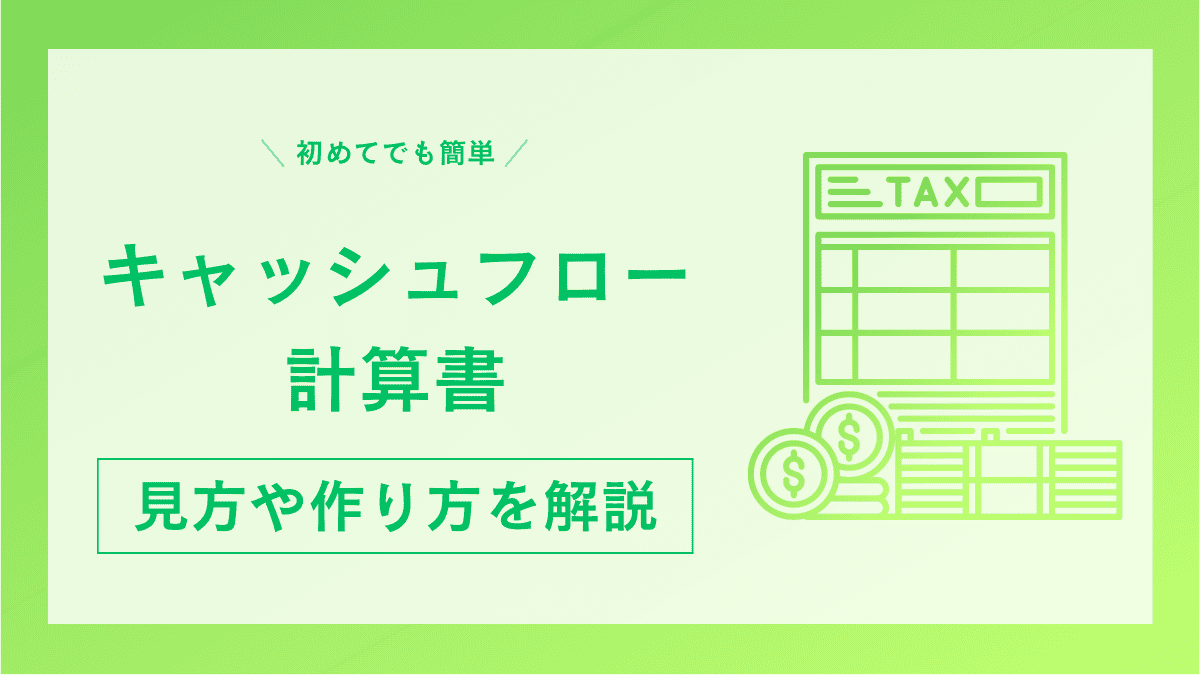
お金の出入りを表す財務三表のひとつ
キャッシュフローは、キャッシュ=お金、フロー=流れを表しており、キャッシュフロー計算書はお金の流れを表している財務諸表のことです。
また、キャッシュフロー計算書は貸借対照表・損益計算書とあわせて財務三表と呼ばれていることからも、重要な計算書類ということが分かるでしょう。
経営状況を把握するための資料
キャッシュフロー計算書は、経営状況を把握するための資料で、キャッシュフロー計算書を読み解くには下記の4つの用語の意味を覚えておくと良いでしょう。
・営業活動によるキャッシュフロー
・投資活動によるキャッシュフロー
・財務活動によるキャッシュフロー
・フリーキャッシュフロー
営業活動によるキャッシュフローは、本業の活動の結果を表し、本業でどれだけ稼げているかが分かります。
マイナス符号になっている場合は、一般的に本業で赤字であることを意味するため、初めに確認すべき重要な項目といえるでしょう。
投資活動によるキャッシュフローは、固定資産などの投資に関わる収入と支出のことで、設備投資をするとマイナス、資産を売却するとプラスになります。
また、財務活動によるキャッシュフローは、株式の発行や金融機関からの借入金などの財務活動に関わる収入と支出のことです。
株式の発行をしたり、借り入れをしたりするとキャッシュが入ってくるため、プラス符号になります。
最後にフリーキャッシュフローは、獲得したキャッシュのうち、自由に使えるキャッシュのことを指します。
フリーキャッシュフローを求めるための一般的な計算式は下記の通りのため、覚えておくとよいでしょう。
フリーキャッシュフロー=(営業活動によるキャッシュフロー)ー(投資活動によるキャッシュフロー)
間接法で作成するのが一般的
キャッシュフロー計算書には直接法と間接法の2種類の作成方法がありますが、間接法で作成するのが一般的です。
なぜなら、営業による収入や仕入による支出など、項目ごとに記載をする直接法を採用すると、作成に時間と手間がかかってしまうためです。
間接法は、項目ごとの記載ではなく、貸借対照表と損益計算書を参考にしながら作成できるため、一般的に採用される作成方式といえるでしょう。
なお、直接法と間接法のどちらの方式を採用しても、内訳は変わるものの、合計金額は変わらないことを覚えておいてください。
キャッシュフロー計算書で減価償却費をプラス計上する理由
キャッシュフロー計算書で減価償却費をプラス計上する理由は、減価償却費が現実には出ていない費用であるためです。
損益計算書では減価償却費が計上されれば利益が減りますが、減価償却費は現実には出ていない費用、つまり現金の支出を伴わない費用です。
したがって、現金の出入りを表すキャッシュフロー計算書と損益計算書で減価償却費の扱い方が異なるため、キャッシュフロー計算書で減価償却費をプラスすることになります。
そこで、ここでは下記の通り、具体例を挙げて詳しく解説していきます。
1.固定資産の購入で現金が減る
2.損益計算書では減価償却費をマイナス計上する
3.マイナス計上した分を補正するためにプラスにする
1から順番に解説していくので、理解を深めていきましょう。
1.固定資産の購入で現金が減る
例えば、購入価格100万円、定額法で耐用年数4年のパソコンを現金一括払いで購入した場合を考えてみましょう。
キャッシュフロー計算書では、現金の出入りを記録するため、購入した際に100万円の現金が減ったものとして記録します。
なお、キャッシュフロー計算書は一般的に用いられる間接法で作成することとします。
2.損益計算書では減価償却費をマイナス計上する
パソコンを使用し始めると、損益計算書で減価償却費を計上する必要があります。
損益計算書とキャッシュフロー計算書の関係性を表したのが、下記の表です。
| 経過年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 | ▲25万円 | ▲25万円 | ▲25万円 | ▲25万円 |
| キャッシュフロー計算書 | ▲100万円 |
損益計算書では、購入価格100万円、定額法で耐用年数4年で減価償却を行うため、毎年▲25万円の減価償却費を計上します。
一方キャッシュフロー計算書は、現金の出入りを表すため、購入時の1年目に▲100万円を記録します。
3.マイナス計上した分を補正するためにプラスにする
損益計算書では、毎年▲25万円の減価償却費が利益から差し引かれていきます。
損益計算書では減価償却費分の利益が減っていますが、減価償却費は他の費用とは異なり、計上しても現金が出ていくわけではないため、現金の流れに影響を与えません。
そこで、損益計算書で減価償却費をマイナス計上した分を補正するために、キャッシュフロー計算書で減価償却費分をプラスにし、損益計算書とキャッシュフロー計算書の整合を取ります。
整合を取る理由は、キャッシュフロー計算書の間接法は損益計算書から情報を取るためです。
損益計算書から情報を取っているにもかかわらず、損益計算書との整合が取れないと、キャッシュフロー計算書を正しく作成できません。
したがって、損益計算書とキャッシュフロー計算書の整合を取るために、減価償却費をキャッシュフロー計算書ではプラスにすることになります。
減価償却を正しく活用して現金を増やす方法
前の章で解説した通り、減価償却費はキャッシュフロー計算書の作成の際に調整が必要な項目ですが、減価償却を下記の方法で活用すれば現金を増やせます。
・減価償却で節税する
・設備投資や固定資産の購入で収益を上げる
それぞれ見ていきましょう。
減価償却で節税する
損益計算書で減価償却費を計上すれば、利益が下がるため法人税額も減ります。
そのため、減価償却をすることにより節税して手元の現金が増えるため、正しく減価償却を行うことが大切です。
設備投資や固定資産の購入で収益を上げる
設備投資を行うことで業務の効率化や増産などが期待できるため、これまでの事業活動より収益を上げられる可能性が上がります。
したがって、設備投資をして減価償却費を計上することになるものの、減価償却費以上の収益を上げれば現金が増えることになります。
ただし、採算の取れない、また身の丈に合わない設備投資を行ってしまうと、収益を上げるどころか減価償却費の負担だけが残ることになるため、慎重に協議をした上で設備投資を行うとよいでしょう。
キャッシュフロー計算書と損益計算書で扱いが違う項目
実は減価償却費以外にも、キャッシュフロー計算書と損益計算書で扱いが違う項目があることをご存じでしょうか?
具体的には、下記の4つの項目です。
・非現金支出費用
・仕入債務・売上債権
・受取配当金や支払利息など
・棚卸資産
それぞれ解説しますので、減価償却費以外の項目に注意しながら確認していきましょう。
非現金支出費用
非現金支出費用とは、現金を伴わない費用のことで、代表的なものが本記事で解説している減価償却費です。
減価償却費以外には、賞与引当金・退職給付引当金・貸倒引当金繰入額・のれんの償却額などが挙げられます。
仕入債務・売上債権
仕入債務は、買掛金や支払手形などで仕入れた金額のことで、増えれば損益計算書上の利益はマイナスになります。
ただし、仕入債務が増加した場合、支払時期が来ていないためキャッシュフロー計算書ではプラスで表示します。
一方、売上債権は売掛金や受取手形などで売り上げた金額のことで、増えれば損益計算書上の利益はプラスです。
もし売上債権が増加した場合、現金を回収できていないためキャッシュフロー計算書ではマイナスで表示します。
キャッシュフロー計算書と損益計算書では、表示する符号が異なることに注意をしましょう。
受取配当金や支払利息など
受取配当金や支払利息なども、損益計算書上では実際に受け取っていない配当金や支払っていない利息が含まれるため調整をしなければなりません。
それぞれ調整する項目は、下記の通りです。
・受取配当金:営業活動によるキャッシュフロー
・支払利息:財務活動によるキャッシュフロー
また、実際の受取金額、支払金額にあわせるために、受取配当金が増加した場合はマイナス、支払利息が増加した場合はプラスで調整します。
棚卸資産
商品や仕掛品などの棚卸資産は、期末時点で売れずに在庫に残っているもので、現時点では現金を生み出すものではありません。
したがって、棚卸資産が増えた場合、キャッシュフロー計算書ではマイナスで表示することになります。
まとめ
本記事では、キャッシュフロー計算書で減価償却費をプラス計上する理由について解説しました。
キャッシュフロー計算書で減価償却費をプラスにする理由は、減価償却費が現金の支出を伴わない費用のため、損益計算書とキャッシュフロー計算書の整合を取る必要があるためです。
また、キャッシュフロー計算書でプラス計上する流れは、下記の通りです。
・固定資産の購入で現金が減る
・損益計算書では減価償却費をマイナス計上する
・マイナス計上した分を補正するためにプラスにする
記事内容とあわせて、確認をしておきましょう。
また、減価償却費以外にもキャッシュフロー計算書と損益計算書で扱いが違う項目として、下記の4つの項目があります。
・非現金支出費用
・仕入債務・売上債権
・受取配当金や支払利息など
・棚卸資産
キャッシュフロー計算書の作成の際に理解が必要な項目のため、確実に確認しておきましょう。