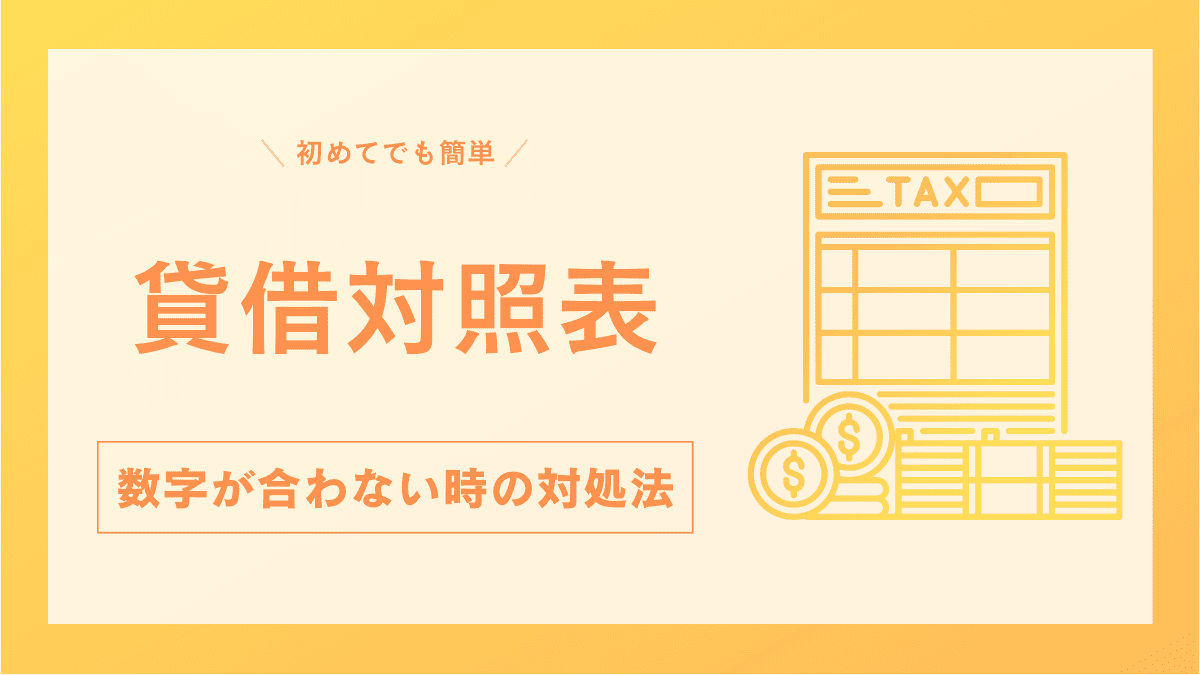企業の決算資料でよく目にする「貸借対照表」。
貸借対照表は企業だけでなく、65万円の青色申告特別控除を受ける個人事業主が、確定申告を行う際に必要になる重要な決算書類です。
しかし、貸借対照表を作成する際に、数字が合わずに困っている人も多いのではないでしょうか?
そこで、本記事では貸借対照表の数字が合わない場合の対応方法を解説していきます。
貸借対照表の見方や仕組みについても解説しますので、貸借対照表の理解を深め、スムーズに貸借対照表の作成をできるようにしましょう。
貸借対照表の数字が合わないとどうなる?
貸借対照表は、ある時点の企業の財政状態を表す重要な決算書類です。
英語の表記は「Balance Sheet」で「B/S(ビーエス)」と頭文字を取って略されて呼ばれることもあります。
重要な決算書類である貸借対照表の数字が合わない場合は、どうなるのでしょうか?
企業でも個人事業主でも、数字が合わないと確定申告に適した書類としてみなされず、所轄の税務署に受理されません。
なぜなら、数字が合わないということは決算が正しくないことを示しているからです。
個人事業主の場合は確定申告が受理されないと、65万円の青色申告特別控除を受けられないため注意が必要です。
次の章で、貸借対照表の見方や仕組みを解説しますので、貸借対照表の作成を適切に進めるために理解を深めていきましょう。
貸借対照表の見方や仕組み
貸借対照表の数字が合わないという状況にならないためには、貸借対照表の理解が必要です。
そこで、ここでは貸借対照表の見方や仕組みについて下記の4つを解説していきます。
● 借方(左側)と貸方(右側)が必ず同額になる
● ポイント➀「自己資本比率」
● ポイント➁「流動比率」
● ポイント➂「当座比率」
1つずつ見ていきましょう。
借方(左側)と貸方(右側)が必ず同額になる
貸借対照表は、借方(左側)と貸方(右側)が必ず同額になる仕組みになっています。
借方と貸方が同額になる理由は、貸借対照表の基になっている仕訳が借方と貸方でそれぞれ同額になっているからです。
したがって、もし貸借対照表の借方と貸方が同額になっておらず数字が合わないときは、仕訳が正しく記録できていないことを意味しています。
正しい貸借対照表は、借方と貸方が必ず同額になることを覚えておきましょう。
ポイント➀「自己資本比率」
ここからは、貸借対照表の見方のポイントを解説していきます。
ポイントの1つ目が「自己資本比率」です。
自己資本比率は、企業の経営が財務的に安定しているかを測る指標の一つで、数値が高いほど経営が安定している企業といえます。
自己資本比率の計算式は、下記の通りです。
自己資本比率(%)=自己資本÷総資産×100
一般的には、50%以上であれば財務状態が健全と考えられ、20%以上あれば一般的な水準と考えられています。
自己資本とは、返済義務のないお金のことで、貸借対照表の中の資本金や利益剰余金が含まれている純資産のことです。
一方、総資産とは貸借対照表の資産のことを指しています。
したがって、自己資本比率から、企業の資産のうち返済義務のないお金がどのくらいの割合を占めているかが分かることを覚えておきましょう。
ポイント➁「流動比率」
ポイントの2つ目が「流動比率」です。
流動比率を見れば、流動資産と流動負債の割合から、企業の短期的な安全性がわかります。
流動比率の計算式は、下記の通りです。
流動比率(%)=流動資産÷流動負債
また、流動資産と流動負債の定義は下記の通りです。
● 流動資産:基本的に1年以内に現金化できる資産。現金、売掛金、棚卸資産など。
● 流動負債:1年以内に返済の必要がある負債。支払手形、未払金、買掛金など。
流動比率は、流動資産を流動負債で割っているため、1年以内に返済する必要がある負債を流動資産で返済できるかを見ていることになります。
もし、流動比率が100%を下回る場合、つまり流動負債が流動資産よりも大きくなってしまうと、資金繰りが厳しいことを意味しているため、財務面で安全とはいえません。
流動比率の数値が小さいほど支払能力がなく倒産する恐れもあるため、流動比率も貸借対照表を見てチェックすべき指標といえるでしょう。
ポイント➂「当座比率」
ポイントの3つ目が「当座比率」です。
当座比率を見れば、流動比率よりもさらに財務面での企業の安全性がわかります。
当座比率の計算式は下記の通りです。
当座比率(%)=当座資産÷流動負債
また、当座資産の定義は下記の通りとなっています。
● 当座資産:流動資産から棚卸資産(商品や仕掛品など)を除いたもの
棚卸資産は、売れ残ったり廃棄されたりする恐れがあるため、1年以内に現金ができない可能性がある資産です。
したがって、流動資産から棚卸資産を除いた当座資産と流動負債を計算式に用いることで、流動比率よりもさらに財務面で安全かどうかを確認できます。
ただし、当座資産は全て現金ではなく、売掛金や未収入金などの回収リスクがある勘定科目も含まれていることに注意が必要です。
当座比率を算出し、勘定科目ごとの残高確認もすることで、財務面の安全性を把握するようにしましょう。
貸借対照表にある3つの項目の勘定科目
前の章では貸借対照表の見方や仕組みを解説しました。
そこで、ここではさらに貸借対照表の理解を深めるために、貸借対照表の内容を細かくみていきます。
貸借対照表には、下記の3つの項目があります。
● 資産
● 負債
● 純資産
さらに3つの項目ごとに勘定科目がわかれているため、項目ごとの勘定科目を確認していきましょう。
「資産」で使われる勘定科目の詳細
まずは「資産」で使われる勘定科目の詳細を見ていきます。
資産は貸借対照表の左側に記載され、流動資産・固定資産・繰延資産の3つにわけられます。
資産で使われる主な勘定科目の詳細は、下記の通りです。
| 流動資産 | |
|---|---|
| 現金預金 | 現金、普通預金、当座預金などの現金及び預金 |
| 売上債権 | 商品やサービスを販売したことにより得た売掛金や受取手形などの債権 |
| 有価証券 | 1年以内に満期になる国債や株券などの有価証券 |
| 棚卸資産 | 商品や仕掛品など将来販売するために保有している在庫 |
| その他の流動資産 | 1年以内に現金化ができる短期貸付金や未収入金など |
| 固定資産 | |
|---|---|
| 有形固定資産 | 土地、建物、機械装置、リース資産、建設仮勘定など |
| 無形固定資産 | のれん、ソフトウェア、電話加入権、特許権など |
| 投資その他の資産 | 投資有価証券、関連会社株式、長期貸付金など |
| 繰延資産 | |
|---|---|
| 創立費、開業費、社債発行費、開発費、株式交付費 | |
貸借対照表の作成の際は、流動資産・固定資産・繰延資産ごとに金額を合計し、全ての項目を合計した金額を「資産合計」として借方(左側)に表示します。
「負債」で使われる勘定科目の詳細
次に「負債」について見ていきましょう。
負債は、流動負債と固定負債にわけられます。
負債で使われる主な勘定科目の詳細は、下記の通りです。
| 流動負債 | |
|---|---|
| 支払手形 | 仕入で発生した手形債務 |
| 買掛金 | 商品の仕入代金を支払う債務 |
| 短期借入金 | 1年以内に返済する借入金 |
| 固定負債 | |
|---|---|
| 社債 | 企業が発行する債券 |
| 長期借入金 | 1年を超えて返済する予定の借入金 |
| 退職給付引当金 | 従業員の退職金などを見積もり、引当金として計上した金額 |
流動負債と固定負債をそれぞれ合計し、全て足して「負債合計」を算出後、貸借対照表の貸方(右側)の上部に表示します。
「純資産」で使われる勘定科目の詳細
最後に「純資産」について確認していきましょう。
純資産は、株主資本、評価・換算差額等・新株予約権の3つにわけられます。
純資産で使われる主な勘定科目の詳細は、下記の通りです。
| 株主資本 | |
|---|---|
| 資本金 | 株主が会社に出資したお金 |
| 新株式申込証拠金 | 新株式を発行して支払われた金額のうち、決算時点で資本金に振り替えられていない金額 |
| 資本剰余金 | 会社設立時などに集められた資金のうち、資本金に計上されなかった金額 |
| 利益剰余金 | これまで企業が稼いだ利益を積み立てたお金 |
| 自己株式 | 株式会社が発行した株式のうち、自社で保有している株式 |
| 評価・換算差額等 | |
|---|---|
| 資産・負債・株主資本に含まれなかった(新株予約権を除く)、その他有価証券評価差額金、繰越ヘッジ損益、為替換算調整勘定など | |
| 新株予約権 | |
|---|---|
| 新株予約権を発行した企業に権利を行使し、その企業の株式の交付を受けられる権利 | |
株主資本、評価・換算差額等、新株予約権をそれぞれ合計し、全て足した金額を貸借対照表の貸方(右側)にある負債の下部に表示します。
また、資産の合計と負債・純資産の合計が必ず一致することも確認しておきましょう。
貸借対照表が合わない場合の5つの確認方法
ここまで貸借対照表の見方や3つの項目について解説しましたが、内容を理解していても数字が合わない経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか。
そこでここでは、貸借対照表が合わない場合の確認方法を5つ解説します。
● 勘定科目の書き方が合っているかを確認する
● 金額の入力ミスがないかを確認する
● 現預金残高と現預金出納帳の金額を確認する
● 源泉徴収税額を確認する
● 仕訳帳や総勘定元帳を確認する
それぞれ確認していきましょう。
勘定科目の書き方が合っているかを確認する
貸借対照表の数字が合わない場合、勘定科目の書き方が合っているかの確認が必要です。
勘定科目の書き方が合っていないと、貸借対照表内で勘定科目の計上場所が間違っている可能性があります。
貸借対照表では、資産が左側、負債・純資産が右側に計上されますが、仕訳や転記をする際に間違ってしまうと数字が合わなくなってしまいます。
例えば、売掛金は資産のため左側、買掛金は負債のため右側、利益剰余金は純資産のため右側に計上されますが、間違っていないでしょうか。
基本的なことですが、仕訳の数が多いと間違っていることに気付きづらいため、まずは勘定科目の書き方が合っているかを確認するとよいでしょう。
金額の入力ミスがないかを確認する
次に、金額の入力ミスがないかを確認しましょう。
仕訳の時点で、借方と貸方それぞれの合計金額が合っていないと、数字は合いません。
もし仕訳の入力を間違ってしまうと、勘定科目の確認の際に異常に大きな金額、もしくは異常に小さな金額で計上されることがあります。
あるいは転記の際に金額の入力ミスをしてしまった可能性も考えられるため、仕訳や転記の際に単純な金額の入力ミスがないかの確認が必要です。
意外と見られるのが、現金などの資産がマイナスになっているケースです。
現金がマイナスというのは現実的に起こらないため、現金を補填した際の仕訳をし忘れていたり、現金勘定の借方と貸方の計上が間違っていたりする場合が想定されます。
さらに、元金と利息をわけて仕訳をしないと、借入金がマイナスになるケースもあるため、注意が必要です。
現預金残高と現預金出納帳の金額を確認する
現預金の残高と現預金出納帳の金額を確認するのも、有効な手段です。
手元で管理している現金残高と、金融機関の口座にある預金残高は現預金出納帳の残高と一致しており、さらに貸借対照表の現金及び預金の残高とも一致するはずです。
しかし、上記のうちどれか1つでも異なる場合は、仕訳もしくは出納帳が間違っていることが考えられます。
例えば、金融機関側では処理されているものの仕訳をしていないケース、また現預金出納帳で金額や日付、また内容の記入が間違っていたケースなどが考えられるでしょう。
もしくは、当期の期首残高から金額が一致していない可能性も考えられます。
現預金残高と現預金出納帳の金額が異なることのないように、確実に確認をしていきましょう。
源泉徴収税額を確認する
個人事業主であれば、源泉徴収の税額が支払調書と一致するかも確認してみましょう。
支払調書は、報酬を支払った企業などが、支払った金額や内容、また支払い先などを記載し、税務署に提出する書類です。
支払調書を見れば源泉徴収税額がわかるため、自身で認識している源泉徴収税額と支払調書の金額に差がないかを確認しましょう。
もし差があれば、売上から源泉徴収された際の仕訳処理が間違っている可能性があるため、確認してみてください。
なお、支払調書は税務署に提出する義務はありますが、報酬を支払った相手に支払調書を送付する義務はありません。
もし取引先から支払調書が送付されていないものの、支払調書の確認をしたい場合は、支払調書の送付が義務ではないことを念頭において、問い合わせをしてみるとよいでしょう。
仕訳帳や総勘定元帳を確認する
これまで挙げた4つの確認方法で詳細を確認し、仕訳帳や総勘定元帳を確認しましょう。
仕訳帳は日々の取引を記録する帳簿、また総勘定元帳は取引を勘定科目ごとに記録する帳簿で、貸借対照表の基となっている主要簿です。
仕訳帳と総勘定元帳をそれぞれ確認することで、どの時点で間違ってしまったかを確認できます。
金額や借方と貸方が正しいかを確認し、間違っていたら修正仕訳の処理をしていきましょう。
貸借対照表が合わない場合に無理やり合わせる方法
個人事業主で、前の章で解説した確認方法を用いても貸借対照表が合わない場合には「事業主貸し借り」を使って、数字を無理やり合わせる方法があります。
個人事業主は、生活費を事業用の口座へ入金したり、反対に事業用の口座から生活費として引き出す場合があります。
上記のように、事業と関係なく資金を入金したり、引き出したりした際に「事業主貸し借り」、厳密には事業主貸(じぎょうぬしかし)勘定と事業主借(じぎょうぬしかり)勘定を使用できます。
どうしても貸借対照表の数字が合わない場合は、事業主貸勘定と事業主借勘定を用いて、合わない分の差額の調整ができることを覚えておきましょう。
しかし、事業主貸し借りを使用して調整できるのは個人事業主だけで、法人は使えない方法です。
もし法人で数字が合わないときは、前の章で解説した方法で合わない箇所を探して修正するしかありません。
ただし個人事業主は事業主貸し借りが使えるといっても、合わないときの最終手段としておき、正しい仕訳かどうかを毎月チェックするなどして、合わない状況にならないことが大切です。
まとめ
本記事では、貸借対照表の数字が合わない場合の対応方法を解説しました。
貸借対照表の数字が合わないと、企業も個人事業主も確定申告に適した書類としてみなされず、所轄の税務署に受理されません。
数字が合うように、適切に貸借対照表を作成していくことが重要です。
また、貸借対照表が合わない場合は、下記の5つの方法で確認をしてみましょう。
● 勘定科目の書き方が合っているかを確認する
● 金額の入力ミスがないかを確認する
● 現預金残高と現預金出納帳の金額を確認する
● 源泉徴収税額を確認する
● 仕訳帳や総勘定元帳を確認する
もし、上記の5つの方法を確認しても、どうしても貸借対照表が合わない場合は「事業主貸し借り」により合わない差額分の調整が可能です。
ただし「事業主貸し借り」は個人事業主のみ使用可能なため、法人の場合は仕訳帳や総勘定元帳などを1つずつ確認していくしかありません。
個人事業主の場合でも「事業主貸し借り」は数字が合わない場合の最終手段のため、数字が合うように仕訳を正しく記録し続けることが大切です。