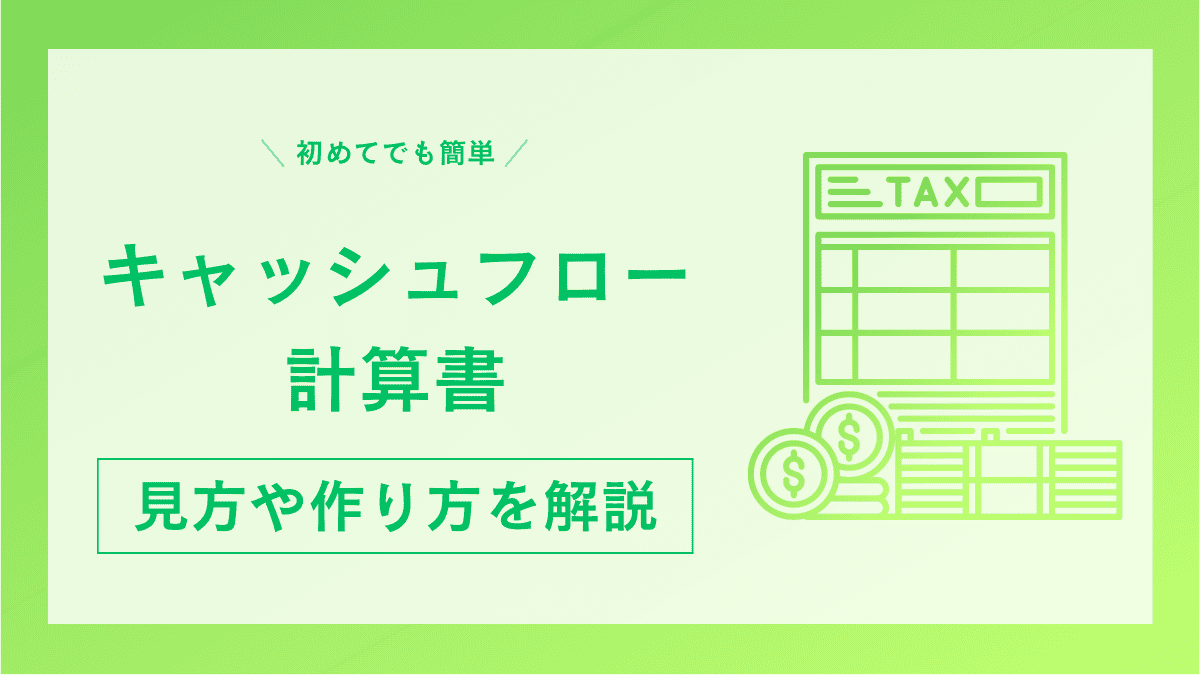「キャッシュフロー計算書」って、何となく聞いたことがあるけど、実際どんなもの?
「義務があるのか分からない」「作り方や見方が難しい」
そんな方のために、本記事ではキャッシュフロー計算書を徹底解説します。
キャッシュフロー計算書は、企業の「お金の流れ」を把握する上で欠かせない重要な財務諸表です。
本記事を参考に、ぜひキャッシュフロー計算書を理解し、自社の財務状況を分析してみましょう。
キャッシュフロー計算書とは?
キャッシュフロー計算書は、企業の「お金の流れ」を把握するための財務諸表の一つです。
具体的には、一定期間における企業の現金の増減を、営業活動、投資活動、財務活動の3つに分類して示します。
損益計算書では、売上や費用を発生主義で計上するため、必ずしも現金の動きと一致しません。
一方、キャッシュフロー計算書は現金主義で作成するため、実際の現金の増減を把握することができます。
キャッシュフロー計算書の作成の義務は?
2005年4月1日から施行された金融商品取引法に基づき、一定規模以上の企業は、キャッシュフロー計算書の作成及び提出が義務付けられています。
・有価証券報告書提出会社
・資本金1億円以上の株式会社
・総資産額500億円以上の非株式会社
上記に該当する企業は、毎事業年度、キャッシュフロー計算書を作成し、財務諸表に添付する必要があります。
※ 提出義務のない中小企業でも、キャッシュフロー計算書を作成することは非常に重要です。
キャッシュフロー計算書の作成・分析の重要性
キャッシュフロー計算書を作成・分析することで、以下のメリットを得ることができます。
企業の資金繰りの状況を把握できる: キャッシュフロー計算書は、企業の現金の動きを把握することができます。これにより、資金繰りの状況を把握し、資金不足のリスクを回避することができます。
経営分析に役立つ: キャッシュフロー計算書は、企業の収益性、投資効率、財務安定性を分析するのに役立ちます。これにより、経営課題を早期に発見し、適切な対策を講じることができます。
投資家や金融機関からの評価を高める: キャッシュフロー計算書は、投資家や金融機関にとって、企業の財務状況を判断する重要な情報です。キャッシュフロー計算書を作成することで、投資家や金融機関からの評価を高めることができます。
中小企業であっても、キャッシュフロー計算書を作成することは、経営の健全化にとって非常に重要です。
キャッシュフロー計算書の作り方
キャッシュフロー計算書は、直接法と間接法の2つの方法で作成することができます。
直接法と間接法の違い
| 直接法 | 間接法 | |
| 作り方 | 営業活動における主要な現金収入・支出項目を直接計上する | 損益計算書の項目を調整して、キャッシュフローを算出する |
| 利点 | 比較的分かりやすい | 損益計算書との整合性が取れている |
| 欠点 | 一部の項目の計上が複雑 | 損益計算書の項目を調整する必要があるため、理解が難しい |
中小企業の場合、直接法の方が比較的分かりやすく作成しやすいため、一般的に直接法が採用されています。
直接法によるキャッシュフロー計算書の作り方
直接法によるキャッシュフロー計算書は、以下の3つの活動に分類して作成します。
1. 営業活動によるキャッシュフロー
売上高
売上原価
人件費
減価償却費
営業利益
営業外収益
営業外費用
営業活動によるキャッシュフロー
2. 投資活動によるキャッシュフロー
売却益
固定資産取得価額
投資活動によるキャッシュフロー
3. 財務活動によるキャッシュフロー
借入金
社債発行
借入金返済
社債償還
配当金
財務活動によるキャッシュフロー
上記それぞれの項目の金額を合計することで、期末現金残高を算出することができます。
間接法によるキャッシュフロー計算書の作り方
間接法によるキャッシュフロー計算書は、損益計算書の税引前当期純利益を起点として、非資金損益項目、営業外収益・費用、特別利益・特別損失を調整することで、営業活動によるキャッシュフローを算出します。
その後、投資活動と財務活動の項目を調整することで、期末現金残高を算出することができます。
キャッシュフロー計算書の見方
キャッシュフロー計算書は、3つの活動に分類して作成されています。
- 営業活動によるキャッシュフロー: 企業の 本業 で稼いだキャッシュフロー
- 投資活動によるキャッシュフロー: 設備投資や有価証券投資など、 将来の成長 に向けた投資活動によるキャッシュフロー
- 財務活動によるキャッシュフロー: 借入金や社債の調達・返済、配当金の支払いなど、 資金調達・返済 に関わるキャッシュフロー
それぞれの活動によるキャッシュフローを分析することで、企業の財務状況 を多角的に把握することができます。
各活動によるキャッシュフローの分析
1. 営業活動によるキャッシュフロー
営業利益: 本業で稼いだ利益が、実際に現金として回収できているかどうかを確認します
営業外収益・費用: 本業以外の活動で発生した収益・費用の影響を把握します。
営業活動によるキャッシュフロー: 本業でどれだけキャッシュを生み出せているかを確認します。プラスであることが望ましいです。
2. 投資活動によるキャッシュフロー
売却益: 固定資産を売却して得たキャッシュを確認します。
固定資産取得価額: 設備投資など、将来の成長に向けた投資にどれだけ資金を投じているかを確認します。プラスであることが望ましいです。
投資活動によるキャッシュフロー: 投資活動によって、どれだけキャッシュが減増したかを確認します。
3. 財務活動によるキャッシュフロー
借入金: 借入金によって調達した資金を確認します。
社債発行: 社債発行によって調達した資金を確認します。
借入金返済: 借入金の返済状況を確認します。プラスであることが望ましいです。
社債償還: 社債の償還状況を確認します。プラスであることが望ましいです。
配当金: 株主へ支払った配当金の状況を確認します。
財務活動によるキャッシュフロー: 資金調達・返済、配当金支払いによって、どれだけキャッシュが減増したかを確認します。
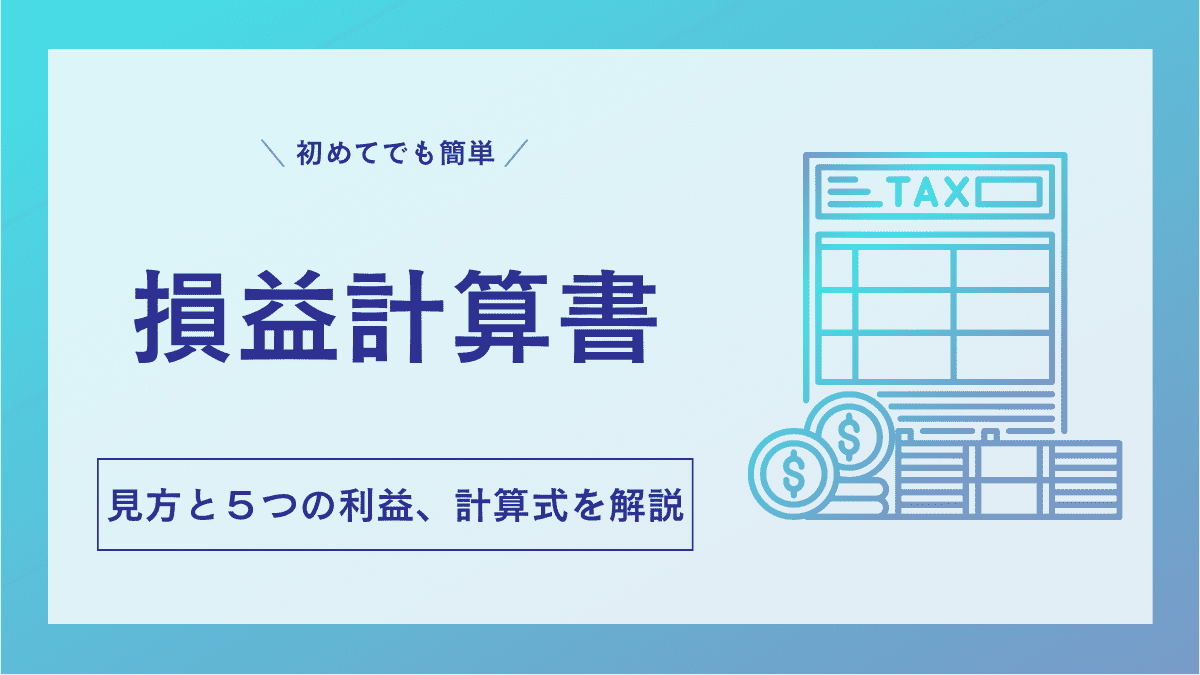
主要なキャッシュフロー比率の分析
キャッシュフロー計算書から算出できる主要な比率は以下の通りです。
営業キャッシュフローマージン: 営業利益がどれだけ現金として回収できているかの割合を示します。高いほど、本業で効率的にキャッシュを生み出せていることを示します。
フリーキャッシュフロー: 本業で稼いだキャッシュから、投資活動に必要な資金と、株主への配当金を支払った後の残りのキャッシュフローを示します。フリーキャッシュフローがプラスであることが望ましいです。
債務資本利息 покрытие率: 営業利益で、支払利息をどれだけ支払うことができるかを表します。1倍以上であることが望ましいです。
キャッシュフロー計算書と他の財務諸表との比較分析
キャッシュフロー計算書は、損益計算書や貸借対照表と比較することで、より深い分析が可能になります。
・損益計算書: 損益計算書は、発生主義で作成されるため、必ずしも現金の動きと一致しません。一方、キャッシュフロー計算書は現金主義で作成されるため、実際の現金の増減を把握することができます。
・貸借対照表: 貸借対照表は、特定の時点における企業の財務状況を示します。一方、キャッシュフロー計算書は、一定期間における企業の現金の動きを示します。
まとめ
本記事では、キャッシュフロー計算書の基本的な知識から、作り方、見方までを解説しました。
キャッシュフロー計算書を理解し、分析することで、以下のメリットを得ることができます。
● 企業の資金繰りの状況を把握できる
● 経営分析に役立つ
● 投資家や金融機関からの評価を高める
中小企業であっても、キャッシュフロー計算書を作成することは、経営の健全化にとって非常に重要です。
ぜひ、本記事を参考に、キャッシュフロー計算書を理解し、自社の財務状況を分析してみてください。