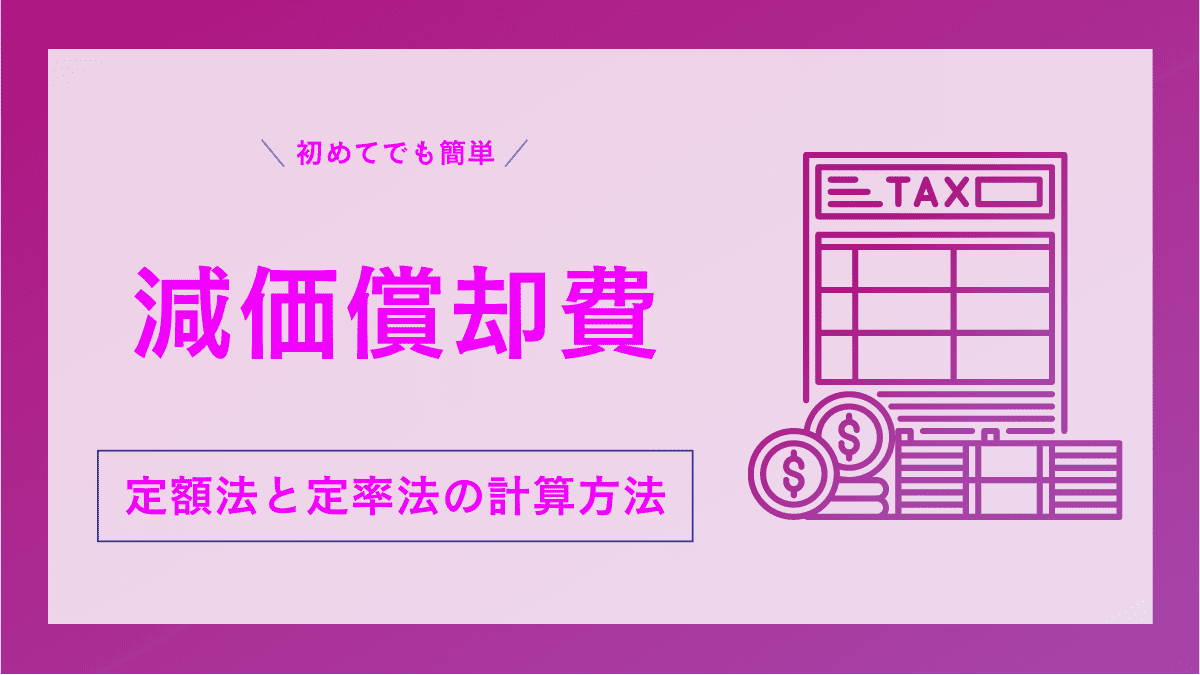減価償却費は、固定資産の購入金額を適切に費用化するために使う勘定科目です。
ただし、減価償却費の意味を知っていても、定額法と定率法の計算方法について詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では、減価償却費の定額法と定率法の計算方法について徹底解説していきます。
さらに、定額法と定率法の計算時のポイントや法改正による計算時の注意点なども解説するので、減価償却費の計算方法を詳しく知りたい人はぜひ最後までお読みください。
減価償却で用いられる用語解説
減価償却費の計算方法を解説する前に、減価償却で用いられる用語を解説していきます。
解説するのは、下記の3つの用語です。
・減価償却費
・法定耐用年数
・取得価額
3つの用語とも減価償却費を理解する上で大切な用語のため、それぞれ確認していきましょう。
減価償却費とは
減価償却費とは、固定資産の購入金額を税法によって定められた耐用年数をもとに、適切に配分するために使用する勘定科目です。
例えば、耐用年数4年のフォークリフトを100万円で購入した場合、使用開始した年に一括で費用にせず、減価償却費を用いて4年にわたって計上していきます。
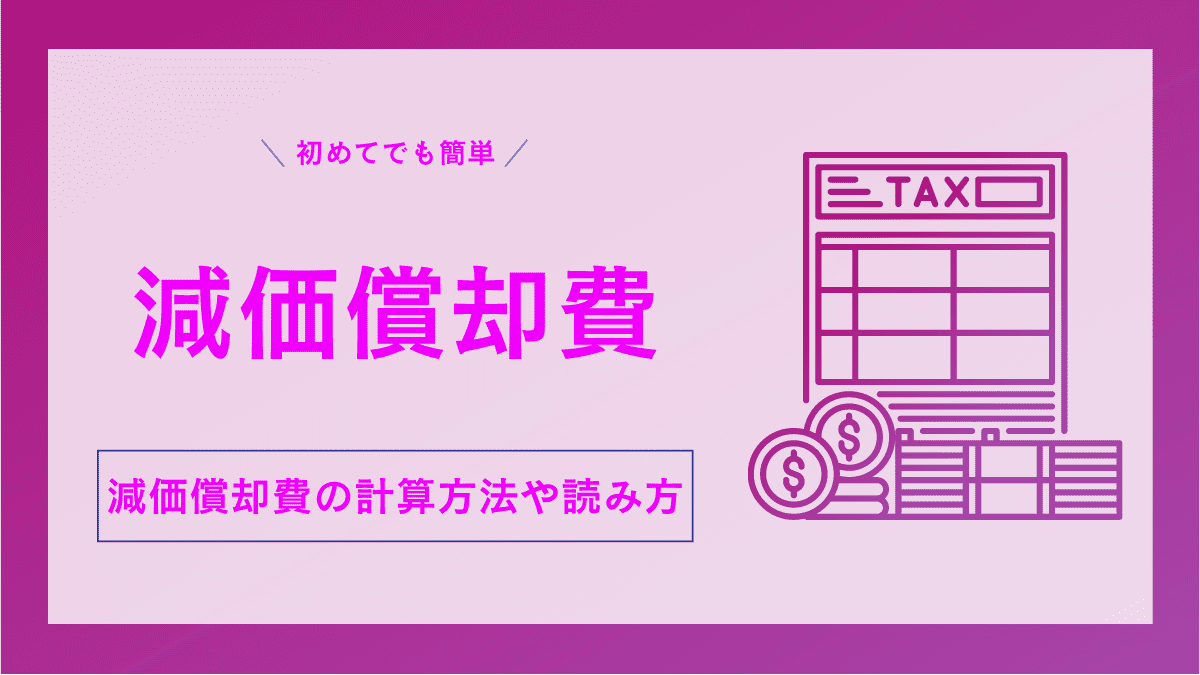
法定耐用年数とは
法定耐用年数とは、固定資産を使用できる期間のことです。
耐用年数は税法により定められており、下記の国税庁のホームページで資産ごとの耐用年数を確認できます。
出典:国税庁「減価償却資産の償却率等表」
取得価額とは
取得価額とは、固定資産を購入した金額のことで、購入するためにかかった手数料や保険料なども付随費用として含まれます。
減価償却のメリット
減価償却を行うと、どのようなメリットがあるのでしょうか?
減価償却を行う主なメリットは、下記の3つです。
・節税ができる
・資産が手元に残る
・損益を正しく把握できる
それぞれ解説していきます。
節税ができる
減価償却費を計上すれば利益が減るため、利益をもとに計算する法人税が減り、節税ができます。
減価償却費を適切に計上し、耐用年数をもとに長期的に計上することで節税効果を得ましょう。
資産が手元に残る
減価償却費は、現金の支出を伴わずに計上する費用です。
したがって、現金つまり資産を減らすことなく、手元に残した状態で減価償却費を費用として計上できます。
損益を正しく把握できる
減価償却を行えば、費用と収益が対応する形で損益計算を適切に行う「費用収益対応の原則」を守り、損益を正しく把握できます。
例えば、工場に機械装置を導入し、使用を開始した初年度に一括で費用を計上してしまったらどうなってしまうでしょうか?
初年度は、機械装置が生み出す利益に対して減価償却費が大きすぎてしまい、2年目以降は減価償却費の発生がなく、利益だけ計上することになってしまいます。
このような損益計算では、費用と収益が対応しているとはいえず、実際の機械装置の稼働状況とも合っていません。
したがって、減価償却には損益を正しく把握できるメリットがあるといえるでしょう。
減価償却の方法は主に「定額法」と「定率法」の2種類
減価償却の方法は、主に定額法と定率法の2種類があるため、それぞれの特徴をとらえることが大切です。
そこで、ここでは下記の4つについて解説していきます。
・定額法と定率法それぞれの特徴
・法人税法上は原則「定率法」を用いる
・「定率法」以外を用いる場合は申請が必要
・資産の種類別の償却方法一覧表
それぞれ確認することで、減価償却方法の理解を深めましょう。
定額法と定率法それぞれの特徴
定額法と定率法のそれぞれの特徴をまとめた表は、下記の通りです。
| 定額法 | 定率法 | |
| 特徴 | 初年度から最終年度まで常に同じ金額で減価償却費を計上する | ・初年度に多額の減価償却費を計上し、年が経過するごとに減っていく ・減価償却費が償却保証額を下回った場合、改定償却率で計算する |
| 計算方法 | 取得価額×定額法の償却率 | ・帳簿価額×定率法の償却率 ・減価償却費が償却保証額を下回ったら改定取得価額※×改定償却率で計算する |
| 留意点 | ・個人事業主が採用する計算方法 ・建物、建物付属、構築物、ソフトウェアは法人・個人事業主関係なく定額法を採用する | ・法人は、建物、建物付属、構築物、ソフトウェア以外の資産で定率法を採用する。 ただし管轄する税務署に申請すれば、建物、建物付属、構築物、ソフトウェア以外の資産について、法人も定額法で計算できる ・個人事業主も管轄の税務署へ申請すれば定率法で計算できる |
※改定取得価額は、保証額>償却額になった最初の会計年度の期首帳簿価額のこと。
定額法と定率法で大きく異なるのは計算方法で、定額法が毎年同じ減価償却費を計上するのに対し、定率法は初年度に多額の減価償却費を計上し、年が経過するごとに減価償却費が減っていく特徴があります。
法人税法上は原則「定率法」を用いる
法人は、会計上は定額法による計算方法も選択可能ですが、法人税法上は原則定率法を用います。
ただし、建物・建物付属・構築物・ソフトウェアの資産については、定額法で減価償却を行うことに注意しましょう。
「定率法」以外を用いる場合は申請が必要
法人で定率法以外、例えば定額法の減価償却を行いたい場合は、管轄の税務署へ申請が必要です。
行っている事業により、定率法と定額法のどちらの計算方法が有利かを確認しておくとよいでしょう。
資産の種類別の償却方法一覧表
資産の種類別で償却方法をまとめた表は、下記の通りです。
| 資産の種類 | 償却方法 |
| 建物、建物付属 | 定額法 |
| 構築物 | 定額法 |
| ソフトウェア | 定額法 |
| 機械装置 | 定額法or定率法 |
| 工具 | 定額法or定率法 |
建物・建物付属・構築物・ソフトウェアは定額法、機械装置・工具は申請をすれば定率法だけでなく定額法による償却も可能です。
【定額法】減価償却費の計算方法
減価償却費を計算する際は、主に定額法・定率法の2つの計算方法があります。
ここでは定額法の計算式と計算の例、さらにメリットとデメリットも解説していきます。
定額法の計算式
定額法の計算式は下記の通りです。
定額法:取得価額×償却率(定額法)
定額法は、上記の計算式により毎年均等に計上するのが特徴です。
償却率を確認したい人は、下記の国税庁のホームページをご覧ください。
出典:国税庁「減価償却資産の償却率等表」
定額法の計算の例
耐用年数が5年で100万円の測定工具を購入して使用開始したケースで、定額法の計算例を解説します。
国税庁のホームページを確認すると、定額法で耐用年数5年の償却率は0.200です。
年数ごとにまとめた表は、下記の通りです。
| 年数 | 減価償却費 | 計算式 |
| 1年 | 20万円 | 100万円×0.200 |
| 2年 | 20万円 | 100万円×0.200 |
| 3年 | 20万円 | 100万円×0.200 |
| 4年 | 20万円 | 100万円×0.200 |
| 5年 | 19万9,999円 | 1円を残して償却 |
耐用年数の最終年の5年目は、使用中であることを示すために帳簿価額を1円残した形で償却を行います。
定額法のメリットとデメリット
定額法は、上の表からも分かる通り、計算が簡単なため手間と時間がかからないメリットがあります。
したがって、減価償却費の見込金額の算出も容易に行えます。
また、減価償却費の計上初年度に利益を確保したい場合、定率法では初年度に多額の計上があるため、定額法で計算した方がメリットがあるといえるでしょう。
一方デメリットは、初年度は定率法よりも定額法の方が減価償却費が少なく、利益が大きいため、節税効果が期待できないことです。
また、法人の場合は建物・建物付属・構築物・ソフトウェア以外の固定資産は基本的に定率法で計算するため、定額法で計算するには管轄の税務署に申請が必要なこともデメリットとして挙げられます。
【定率法】減価償却費の計算方法
次に、定率法の計算の仕方を解説します。
定額法と同様に、メリットとデメリットもあわせて解説するので参考にしてください。
定率法の計算式
定率法は、下記の計算式により減価償却費を求めます。
定率法:帳簿価額(未償却残高)×償却率(定率法)
定額法と大きく異なる点は、取得価額ではなく、償却して残った金額の帳簿価額(未償却残高)を用いて計算を行う点です。
定率法の計算の例
定額法で挙げた例と同様に、ここでも耐用年数が5年で100万円の測定工具を購入して使用開始したケースで、定率法の計算例を解説します。
国税庁のホームページを確認すると、定率法で耐用年数が5年の償却率などは下記の通りです。
・償却率:0.400
・改定償却率:0.500
・保証率:0.10800
上記数値を使用して、年数ごとにまとめた表は、下記の通りです。
| 年数 | 減価償却費 | 計算式 |
| 1年 | 40万円 | 100万円×0.400 |
| 2年 | 24万円 | (100万円-40万円)×0.400 |
| 3年 | 14万4,000円 | (100万円-40万円-24万円)×0.400 |
| 4年 | 10万8千円 | (100万円-40万円-24万円-14万4,000円)×0.500※改定償却率を使用 |
| 5年 | 10万7,999円 | 1円を残して償却 |
定率法の場合は定率法の償却率を使用して求めた減価償却費が、償却保証額に比べて小さい金額になった場合、改定取得価額に改定償却率をかけて減価償却費を求めます。
上記の例の場合、償却保証額は10万8千円(取得価額:100万円×保証率:0.10800)のため、4年目から、改定償却率を使用した計算方法に切り替わることに注意が必要です。
そして、5年目は定額法と同様に、帳簿価額を1円残して償却を行います。
定率法のメリットとデメリット
定率法は、初年度に多額の減価償却費が発生する計算方法になっています。
そのため、利益が大きい会計年度に減価償却を開始すれば、節税効果を大きく受けられることがメリットです。
さらに、建物などを除けば原則定率法で計算することになるため、定率法で計算するための申請が不要な点もメリットに挙げられます。
一方デメリットは、計算方法がわかりづらく複雑な点です。
前の章の計算式をご覧になって分かる通り、定額法の計算にはない保証率と改定償却率を考慮しなければいけないため注意をしてください。
「定額法」「定率法」計算時のポイント
基本的な計算方法は前の章で解説した通りですが、ここでは下記の条件での計算方法を解説していきます。
・中古で購入した場合の計算方法
・年の途中で購入した場合の計算方法
・処分した場合の計算方法
・売却した場合の計算方法
・個人利用資産を事業用に転用した場合の計算方法
一つずつ確認していきましょう。
中古で購入した場合の計算方法
中古で資産を購入したときは、通常の新品の資産を購入した場合と比べて耐用年数が異なり、購入してから使用できる期間を見積もってから、減価償却費の計算をします。
ただし、使用できる期間の見積もりが難しい場合は、下記の計算方法で耐用年数を算出してください。
1.中古資産を取得時、既に全ての耐用年数を経過した場合:法定耐用年数の20%
2.法定耐用年数の一部を経過した場合:(法定耐用年数ー経過した年数)+(経過した年数×20%)
それぞれ具体例を見ていきましょう。
1つめのケース
まずは1つめのケースを考えるにあたり、条件を下記の通りとします。
・中古の機械装置を購入
・法定耐用年数は10年
・使用を開始してから12年が経過
上記の場合、中古資産を購入した時点で耐用年数を経過しているため、法定耐用年数(10年)の20%、つまり耐用年数を2年として減価償却費を計算していきます。
なお、計算結果については端数は切り捨てで、2年未満になったら耐用年数が2年になることに注意をしてください。
2つめのケース
続いて2つめのケースを考えるにあたって、条件を下記とします。
・中古の機械装置を購入
・法定耐用年数は10年
・使用を開始してから4年が経過
1のケースと異なるのが、4年が経過していることです。
2のケースの計算式は下記の通りです。
(法定耐用年数(10年)ー経過年数(4年))+(経過年数(4年)×20%)=6年
したがって、耐用年数を6年として減価償却費を計算していきます。
購入した中古資産の状況により、上記の計算式をご利用ください。
年の途中で購入した場合の計算方法
年の途中で資産を購入した場合は、月割計算をして減価償却費を計上していきます。
下記の前提条件で考えてみましょう。
・会計期間は1月~12月
・300万円のフォークリフトを取得
・フォークリフトの開始月は4月
・耐用年数4年の定額法で計算(償却率:0.250)
上記の条件で計算した場合、減価償却費は下記のように求められます。
300万円×0.250×(9÷12)=56万2,500円
フォークリフトを4月から12月の9ヶ月の間使用したため、1年間の減価償却費を計算した後に、9ヶ月分の計算を含めます。
処分した場合の計算方法
固定資産を処分した場合は、処分した時点の帳簿価額を「固定資産除却損」に振り替える仕訳をします。
取得価格100万円、減価償却累計額が80万円の車両運搬具を処分した場合、間接法の仕訳は下記の通りです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 減価償却累計額 | 800,000円 | 車両運搬具 | 1,000,000円 |
| 固定資産除却損 | 200,000円 |
除却時の帳簿価額が固定資産除却損として計上されます。
売却した場合の計算方法
売却した場合、売却金額が売却時点の帳簿価額より高ければ売却益を計上し、反対に帳簿価額より低ければ売却損を計上します。
売却益
まずは、売却益の仕訳例を考えていきましょう。
取得価額300万円、減価償却累計額270万円、帳簿価額30万円の機械装置を、現金50万円で売却した場合の間接法の仕訳は、下記の通りです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 減価償却累計額 | 2,700,000円 | 機械装置 | 3,000,000円 |
| 現金 | 500,000円 | 固定資産売却益 | 200,000円 |
帳簿価額が30万円に対して売却金額が50万円のため、売却益を20万円計上します。
売却損
次は、売却損の仕訳例です。
取得価額300万円、減価償却累計額270万円、帳簿価額30万円の機械装置を、現金5万円で売却した場合の間接法の仕訳は、下記の通りです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 減価償却累計額 | 2,700,000円 | 機械装置 | 3,000,000円 |
| 現金 | 50,000円 | ||
| 固定資産売却損 | 250,000円 |
帳簿価額が30万円に対して売却金額が5万円のため、売却損を25万円計上します。
個人利用資産を事業用に転用した場合の計算方法
個人事業主の場合、個人で利用していた資産を事業用に転用した場合は、個人利用してきた期間の減価償却費を計算します。
計算する際は、法定耐用年数に1.5をかけた年数をもとに計算を行うことに注意をしてください。
そして、資産の購入金額から計算した減価償却費を引くことで、事業用としての資産の取得価額が決まり、法定耐用年数に基づき計算していきます。
詳細については国税庁のホームページをご覧ください。
出典:国税庁「非業務用資産を業務の用に供した場合」
法改正による計算時の注意点
ここまで減価償却費の計算方法を解説してきましたが、過去に法改正があったため、資産の取得日によって計算方法が変わることに注意が必要です。
定額法と定率法それぞれの計算方法で、法改正前後での計算方法の違いを解説します。
定額法の法改正前後での計算方法の違い
国税庁のホームページにある「減価償却資産の償却率等表」をご覧になって分かる通り、平成19年3月31日以前と平成19年4月1日以降では、償却率が異なります。
詳細をまとめた表は下記の通りです。
| 対象となる資産 | 計算方法 | 計算式 |
| 平成19年3月31日以前に取得した資産 | 旧定額法 | 取得価額×0.9×旧定額法の償却率 |
| 平成19年4月1日以降に取得した資産 | 定額法 | 取得価額×定額法の償却率 |
旧定額法は、上記の計算式で取得価額の5%まで償却した後、翌年以降の5年間で均等償却を行い、1円まで償却します。
一方定額法は、上記の計算式で簿価1円まで償却していきます。
それぞれ計算式が異なるため、十分注意しましょう。
定率法の法改正前後での計算方法の違い
定率法でも、定額法と同様に平成19年3月31日以前と平成19年4月1日以降で計算方法に違いがありますが、さらに平成24年4月1日以降でも計算方法が変わります。
詳細をまとめた表は、下記の通りです。
| 対象となる資産 | 計算方法 | 計算式 |
| 平成19年3月31日以前に取得した資産 | 旧定率法 | 期首帳簿価額×旧定率法の償却率 |
| 平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得した資産 | 250%定率法 | 期首帳簿価額×250%定率法の償却率 |
| 平成24年4月1日以降に取得した資産 | 200%定率法 | 期首帳簿価額×200%定率法の償却率 |
旧定率法は、旧定額法と同様に取得価額の5%まで償却した後、翌年以降の5年間で均等償却をし、帳簿価額1円まで償却します。
250%定率法と200%定率法の計算式は同じですが、償却率が異なるのがポイントです。
指定の償却率を用いて計算をし、帳簿価額1円まで償却します。
定率法でも資産を取得した時期により、減価償却費の計算式が異なることに注意をしてください。
まとめ
本記事では、減価償却費の定額法と定率法について、詳しく解説しました。
定額法で減価償却費を求める計算方法は、下記の通りです。
定額法:取得価額×償却率(定額法)
一方、定率法の計算式は、下記の通りです。
定率法:帳簿価額(未償却残高)×償却率(定率法)
それぞれ計算式が異なるため、十分注意をして計算するようにしてください。
また、それぞれの計算方法でのメリットとデメリットは下記の通りです。
| メリット | デメリット | |
| 定額法 | ・計算が簡単にできる | ・初年度の節税効果が期待できない ・法人の場合、税務署に申請が必要になる |
| 定率法 | ・初年度に節税効果を大きく受けられる ・法人の場合、定率法で計算するための申請をしなくてよい | ・計算方法がわかりづらく複雑になっている |
また、過去に法改正があったため、資産の取得日により減価償却費の計算方法が異なることにも十分注意をして、減価償却費の計算を行うようにしてください。