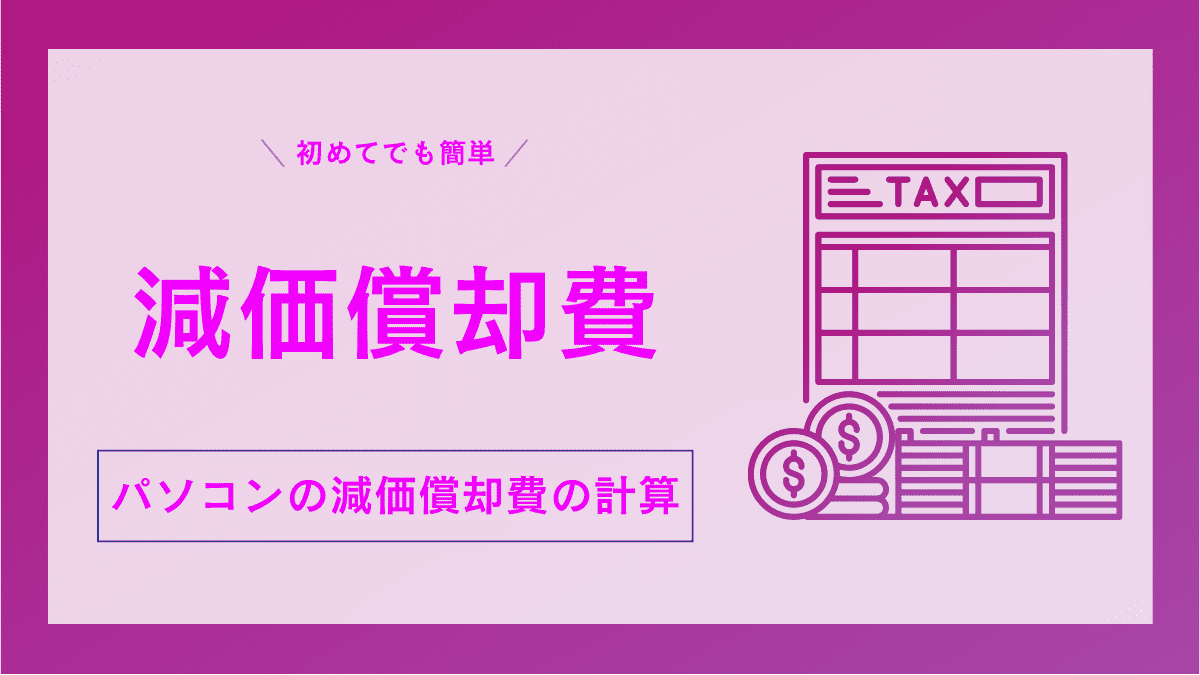「パソコンの減価償却費はどのように計算したらよいのだろう?」
「パソコンの耐用年数は何年なのだろう?」
このようにお悩みではないでしょうか?
パソコンは購入金額ごとに会計処理が変わりますが、詳しく知らない人も多いことでしょう。
そこで、本記事ではパソコンの金額ごとの会計処理方法や、減価償却費の計算方法を解説していきます。
さらに、耐用年数や押さえるべきポイントも解説しますので、パソコンの減価償却費でお悩みの人はぜひ最後までお読みください。
パソコンの減価償却について
ここでは、パソコンの減価償却費を行う上で覚えておくべき点を解説していきます。
・パソコンの減価償却とは
・パソコンの取得価額の算出方法
・パソコンの取得価額に含まれるもの
それぞれ解説しますので、パソコンの減価償却について理解を深めていきましょう。
パソコンの減価償却とは
パソコンの減価償却とは、パソコンの取得価額を購入した年度に一括経費で計上せずに、耐用年数にもとづき、減価償却費を分割して計上することを指します。
費用と収益を対応させる「費用収益対応の原則」という会計上のルールを守るためにも、減価償却は必要な処理といえます。
また、パソコンの減価償却を行う上で大切なことは、パソコンをいくらで取得したかです。
10万円未満であれば、一括で経費計上可能なため、減価償却費として計上をする必要はありません。
一方、10万円以上であれば資産として扱い、減価償却計算を行うことになることを覚えておきましょう。
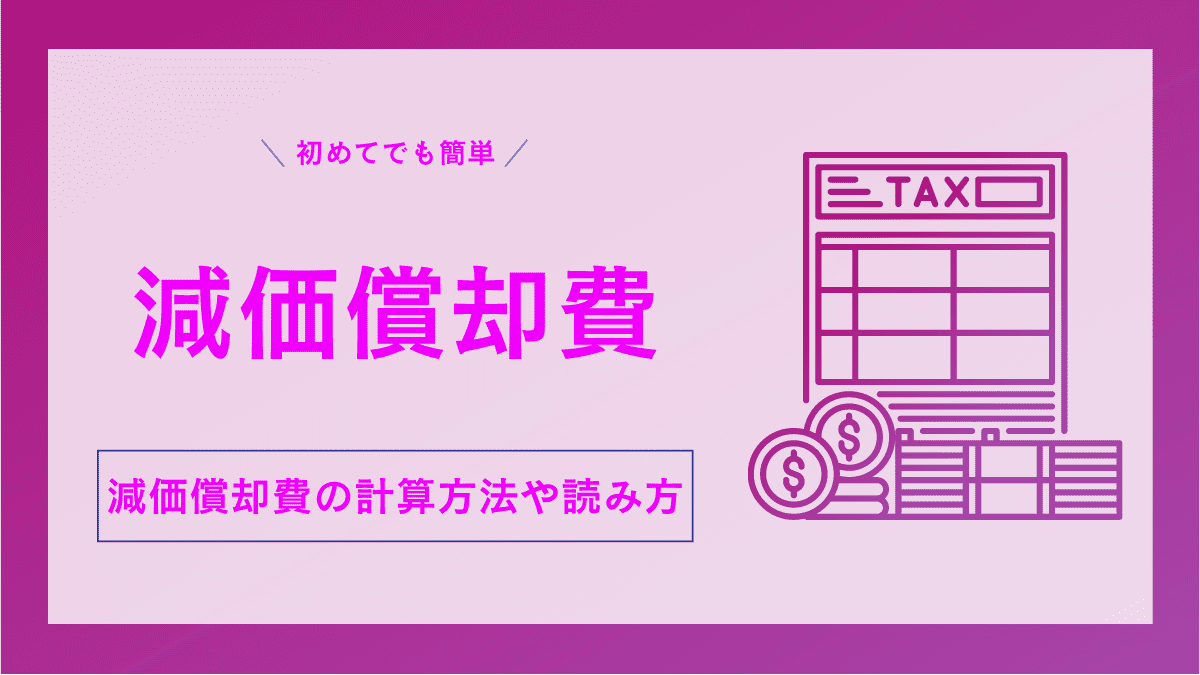
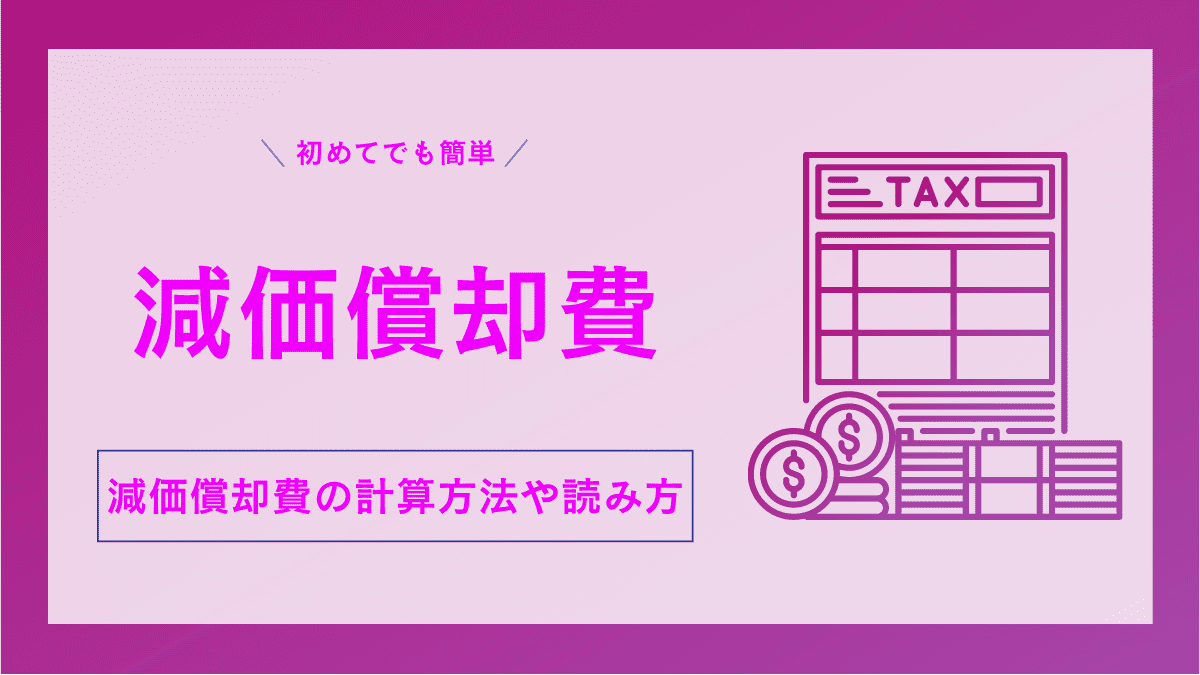
パソコンの取得価額の算出方法
パソコンの取得価額を算出する計算式は、下記の通りです。
パソコンの取得価額=パソコンの購入金額+購入するためにかかった付随費用
ポイントは、購入するためにかかった運送費や購入手数料などの付随費用も取得価額に含めることを忘れずに計上しましょう。
パソコンの取得価額に含まれるもの
パソコン本体だけでなく、一緒に使用する周辺機器を購入したときは、パソコンの取得価額に含めて資産登録をし、減価償却を行います。
パソコン本体以外に取得価額に含める主な例は下記の通りなので、確認しておいてください。
・キーボード
・モニター
・マイク
・Webカメラ
・マウス
パソコンの耐用年数
耐用年数は資産が使用できる期間のことで、パソコンの減価償却を行うために耐用年数を算出することが必要です。
パソコンは、基本的に下記の2つの耐用年数が用いられます。
・サーバー用のパソコン:5年
・サーバー用以外のパソコン:4年
なお、デスクトップパソコン、ノートパソコンによる区別はありません。
注意点が、中古のパソコンを購入した場合の耐用年数の考え方です。
中古のパソコンは取得した時点で価値が下がっており、使用できる期間が短くなっていると考えられます。
したがって、税法で決められた耐用年数でなく、今後使用できる期間を見積った年数で減価償却を行います。
ただし、取得した中古資産が、同じ新品の資産を購入したときの金額の50%を超えるのであれば、税法で決められた耐用年数を適用することに注意をしてください。
なお、もし使用できる期間の見積もりが難しい場合は、簡便法によって計算した年数を採用できます。
簡便法を用いる場合は、下記のどちらのケースにあたるかを判断し、該当する方の計算式を採用してください。
1. 耐用年数を経過していた場合:法定耐用年数×20%
2. 耐用年数の一部を経過していた場合:(法定耐用年数ー経過した年数)+(経過した年数×20%)
なお、上記で計算した結果については端数は切り捨てとなり、2年未満の計算結果になった場合、耐用年数が2年になります。
【10万円未満のパソコン】は減価償却しない
10万円未満のパソコンは減価償却せずに、購入した会計年度に一括で経費を計上できます。
購入金額の全額を経費で計上でき、税務上で損金として算入できるため、節税効果を大きく受けられるといえるでしょう。
ただし、経費で計上しなければならない訳ではありません。
一括償却資産や固定資産に登録をし、減価償却を行うことも可能なため、パソコン購入時の会社の状況から判断するとよいでしょう。
【10万円以上のパソコン】原則減価償却で処理
10万円以上のパソコンは、原則減価償却で会計処理を行います。
金額ごとの会計処理は、下記の通りです。
・10~20万円のパソコンは一括償却資産に該当
・30万円未満のパソコンは少額減価償却資産の特例に該当
・30万円以上のパソコンは通常の減価償却
それぞれ解説していきます。
10~20万円のパソコンは一括償却資産に該当
10~20万円のパソコンは一括償却資産に該当するため、パソコンの耐用年数に関係なく3年で均等償却ができます。
特徴は、資産の登録をする際に年度の合計で登録を行うため、通常の減価償却の手続きに比べて手間がかからないことです。
ただし、一度登録をすると除却を行ったとしても、3年の均等償却を行わなければならないことに注意が必要です。
また、償却資産税の対象にならないため、非課税であることも覚えておきましょう。
30万円未満のパソコンは少額減価償却資産の特例に該当
10万円以上で30万円未満のパソコンは、少額減価償却資産の特例に該当すれば一括で経費計上できます。
青色申告をしている中小企業が少額減価償却資産の特例に該当し、年間300万円まで適用可能です。
なお、償却資産税の対象のため、課税されることには注意をしてください。
30万円以上のパソコンは通常の減価償却
30万円のパソコンは、一括償却資産や少額減価償却資産に該当しないため、通常の減価償却を行う必要があります。
したがって、パソコンの種類により耐用年数を決め、減価償却を行いましょう。
パソコンの減価償却費の計算方法
パソコンの減価償却費の計算方法には、主に定額法と定率法の2つの方法があります。
そこで、それぞれの計算方法について具体例をあげて解説していきます。
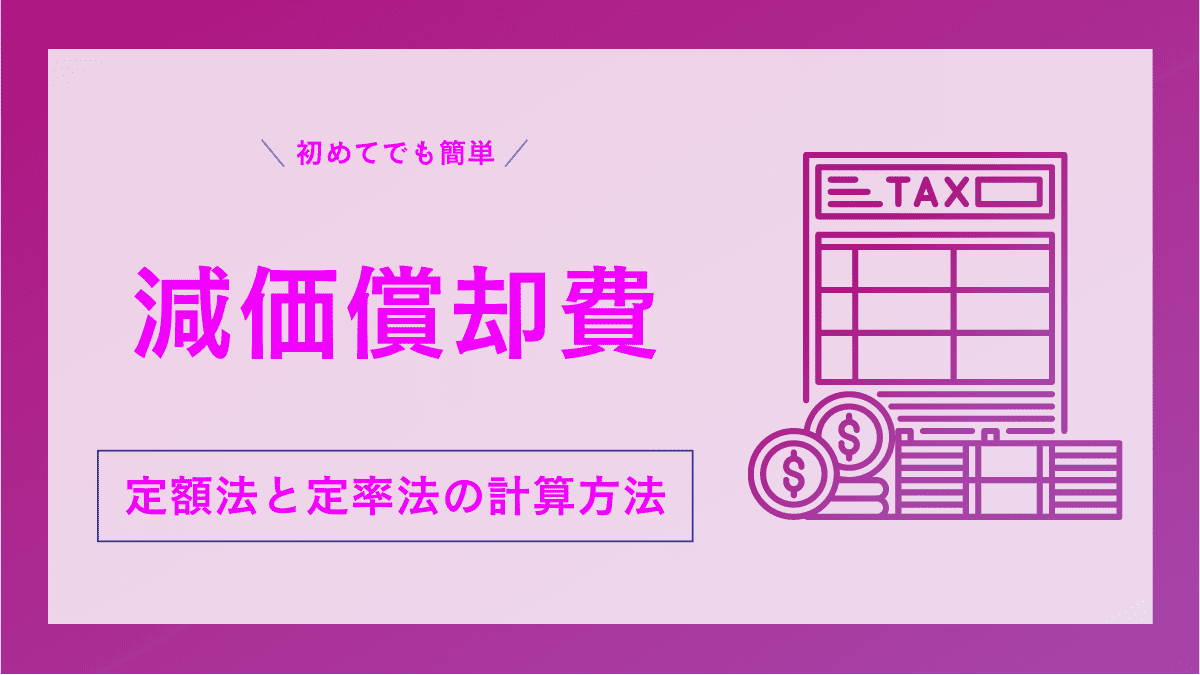
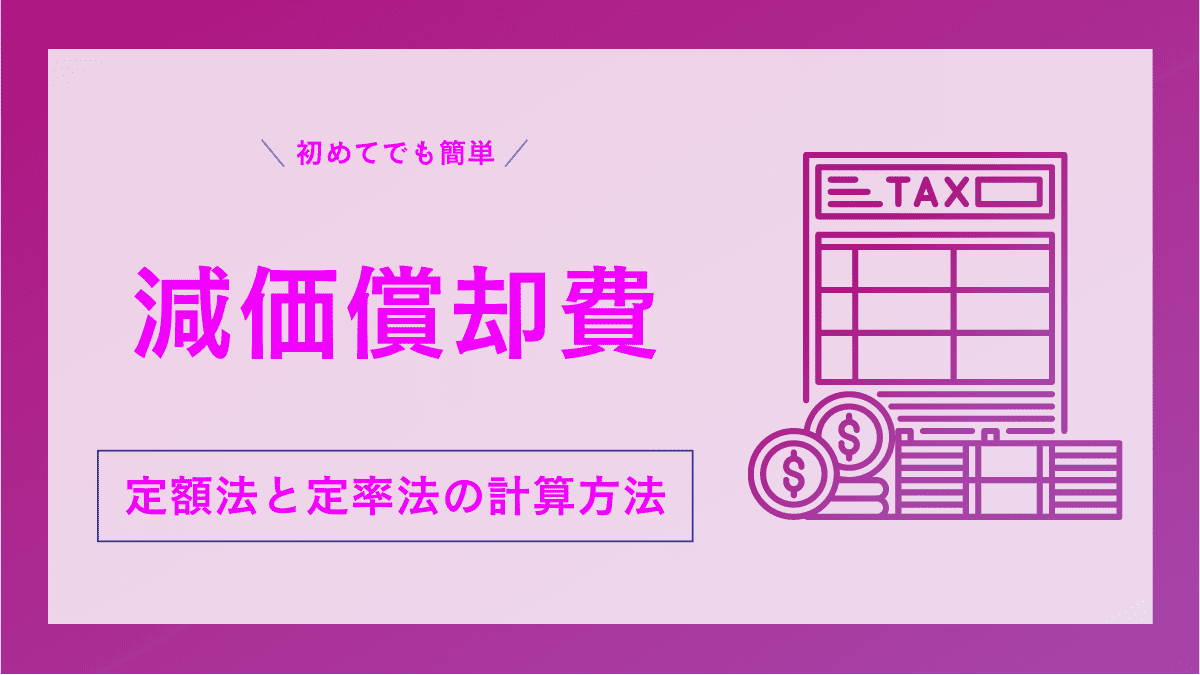
定額法
定額法は、毎年均等に減価償却費を計上する計算方法で、基本的に個人事業主に適用されます。
計算式は下記の通りです。
定額法の減価償却費=固定資産の取得価額×定額法の償却率
ここで、耐用年数が4年(償却率:0.250)のサーバー用以外のパソコン100万円を購入して使用を開始した例を考えてみましょう。
年ごとの減価償却費と計算式は、下記の通りです。
| 年数 | 減価償却費 | 計算式 |
| 1年 | 25万円 | 100万円×0.250 |
| 2年 | 25万円 | 100万円×0.250 |
| 3年 | 25万円 | 100万円×0.250 |
| 4年 | 24万9,999円 | 帳簿価額が1円まで償却 |
1年目から3年目までは25万円ずつ減価償却費を計上し、4年目はパソコンを使用していることを示すために、帳簿価額1円まで償却を行います。
定率法
定率法は、初年度に多額の減価償却費を計上し、年が経過するごとに減価償却費が減っていく計算方法で、基本的に法人に適用されます。
計算式は下記の通りです。
定率法の減価償却費=固定資産の帳簿価額(未償却残高)×定率法の償却率
ここでも、耐用年数が4年(償却率:0.500)のサーバー用以外のパソコン100万円を購入して使用を開始したとしましょう。
年ごとの減価償却費と計算式は、下記の通りです。
| 年数 | 減価償却費 | 計算式 |
| 1年 | 50万円 | 100万円×0.500 |
| 2年 | 25万円 | 50万円(100万円-50万円)×0.500 |
| 3年 | 12万5,000円 | 25万円(50万円-25万円)×0.500 |
| 4年 | 12万4,999円 | 帳簿価額1円を残して償却 |
1年目に取得価額の半分となる50万円の減価償却費を計上し、2年目以降は減っていきます。
そして、4年目は定額法と同様に、帳簿価額1円まで償却を行います。
パソコンの減価償却で押さえるべきポイント
ここまでパソコンの減価償却の計算方法を解説してきましたが、実務上では特殊なケースで計算することもあるでしょう。
そこで、下記の6つのケースの際に押さえるべきポイントを解説していきます。
・中古パソコンは見積り耐用年数で減価償却する
・20万円以内の修理費は経費計上できる
・プライベート兼用のパソコンは按分する
・未使用のパソコンは減価償却資産にならない
・記帳は税込み・税抜きどちらでもOK
・分割払いの場合でも経費にできる
中古パソコンは見積り耐用年数で減価償却する
すでに解説した通り、中古パソコンは、取得時点で今後の使用可能期間を見積もることで耐用年数を決めます。
ただし、見積もりが困難なときは下記の簡便法を用いて、耐用年数の計算が可能です。
1.耐用年数を経過していた場合:法定耐用年数×20%
2.耐用年数の一部を経過していた場合:(法定耐用年数ー経過した年数)+(経過した年数×20%)
なお、求めた年数が端数の場合は切り捨てで、2年未満の場合は耐用年数が2年になります。
それでは、それぞれのケースで耐用年数を算出してみましょう。
1のケース
まずは、1のケースの前提条件を下記として考えていきます。
・中古でサーバー用のパソコンを取得(耐用年数5年)
・取得時、使用期間は7年
上記の場合、耐用年数を超えているため、1の計算式に当てはめた結果は下記の通りです。
法制耐用年数(5年)×20%=1年
計算結果が2年未満の1年になったため、耐用年数が2年になります。
2のケース
続いて、2のケースです。
前提条件を下記の通りとします。
・中古でサーバー用のパソコンを取得(耐用年数5年)
・取得時、使用期間は2年
上記の場合、耐用年数が5年で使用期間が2年のため、2のケースで計算を行いましょう。
(法定耐用年数(5年)ー経過した年数(2年))+(経過した年数(2年)×20%)=3.4年
計算結果が3.4年のため端数切り捨てをして、耐用年数は3年になります。
中古のパソコンを減価償却する際の参考にしてください。
20万円未満の修理費は経費計上できる
パソコンの修理でかかった金額が20万円未満であった場合、一括で経費計上できます。
また、パソコンの機能が向上するような部品交換や修理を行った場合でも、20万円未満であれば一括で経費計上可能です。
ただし、20万円以上で機能向上を行った場合は資本的支出として会計処理し、減価償却を行うことに注意をしてください。
プライベート兼用のパソコンは按分する
個人事業主でプライベート兼用のパソコンを使用している場合の経費は、仕事で使用する分を経費に割り振る、つまり按分することになります。
按分する際は、一日のうち仕事で使用している時間や、一ヶ月のうち仕事で使用している日数など、税務署から問い合わせを受けたときに合理的に説明できる基準にするのが一般的です。
例えば一ヶ月の減価償却費が2万円で、一ヶ月のうち半月を仕事で使用している場合、仕事で使用した割合の50%分の1万円を減価償却費として計上します。
未使用のパソコンは減価償却資産にならない
未使用のパソコンは、減価償却資産になりません。
なぜなら、減価償却費は購入したときに計上されるのではなく、使用が開始されたときから発生するため、減価償却ができないからです。
購入して未使用のままのパソコンは、資産勘定の貯蔵品として計上します。
パソコンを購入したからといって、減価償却の手続きをとらないように注意をしましょう。
記帳は税込み・税抜きどちらでもOK
減価償却費を記帳する際は、消費税額を含んで会計処理する税込経理と、消費税額を含めずに仮払消費税・仮受消費税で分けて会計処理する税抜経理の方法がありますが、税込み・税抜きのどちらでも問題ありません。
ただし、税込で10万円以上のパソコンでも、税抜にすると10万円未満になるのであれば一括で経費計上できるため、税抜の方が優位な面があることを覚えておくとよいでしょう。
分割払いの場合でも経費にできる
パソコンを分割払いした場合でも、一括で経費にできるケースがあります。
経費にできるのは、10万円以上30万円未満のパソコンの場合で、少額減価償却資産の特例が適用されたケースです。
ただし、適用されるのは青色申告をしている中小企業に限られ、上限が年間300万円であることに注意をしてください。
また、分割払いした場合の仕訳についても考えてみましょう。
パソコンの取得価額が27万円で、3回の分割払いをしたときの仕訳例は下記の通りです。
①パソコンを購入したとき
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 消耗品費 | 270,000円 | 未払金 | 270,000円 |
②分割払い1回目から3回目
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
| 未払金 | 90,000円 | 現金 | 90,000円 |
分割払いのため②の仕訳で現金が出ていきますが、①の仕訳の際に一括で消耗品費を計上していることになります。
まとめ
本記事では、パソコンの減価償却費の計算方法について詳しく解説しました。
パソコンの減価償却費は、基本的に定額法か定率法で計算を行います。
注意点は、キーボードやモニターなどの周辺機器も購入した場合は、パソコン本体だけでなく周辺機器も取得価額に含めることです。
また、パソコンの減価償却の際は、基本的に下記の2つの耐用年数を使います。
・サーバー用のパソコン:5年
・サーバー用以外のパソコン:4年
ただし、中古のパソコンを購入したときの耐用年数の考え方には、注意が必要です。
中古のパソコンは、今後使用できる期間を見積った年数で減価償却を行っていきます。
もし、年数を見積もるのが困難な場合は、下記の簡便法による計算方法を活用し、それぞれのケースで使い分けて耐用年数を計算してください。
・耐用年数を経過していた場合:法定耐用年数×20%
・耐用年数の一部を経過していた場合:(法定耐用年数ー経過した年数)+(経過した年数×20%)
さらに、パソコンの減価償却費で押さえるべきポイントも記事内で解説していますので、あわせて確認するようにしてください。