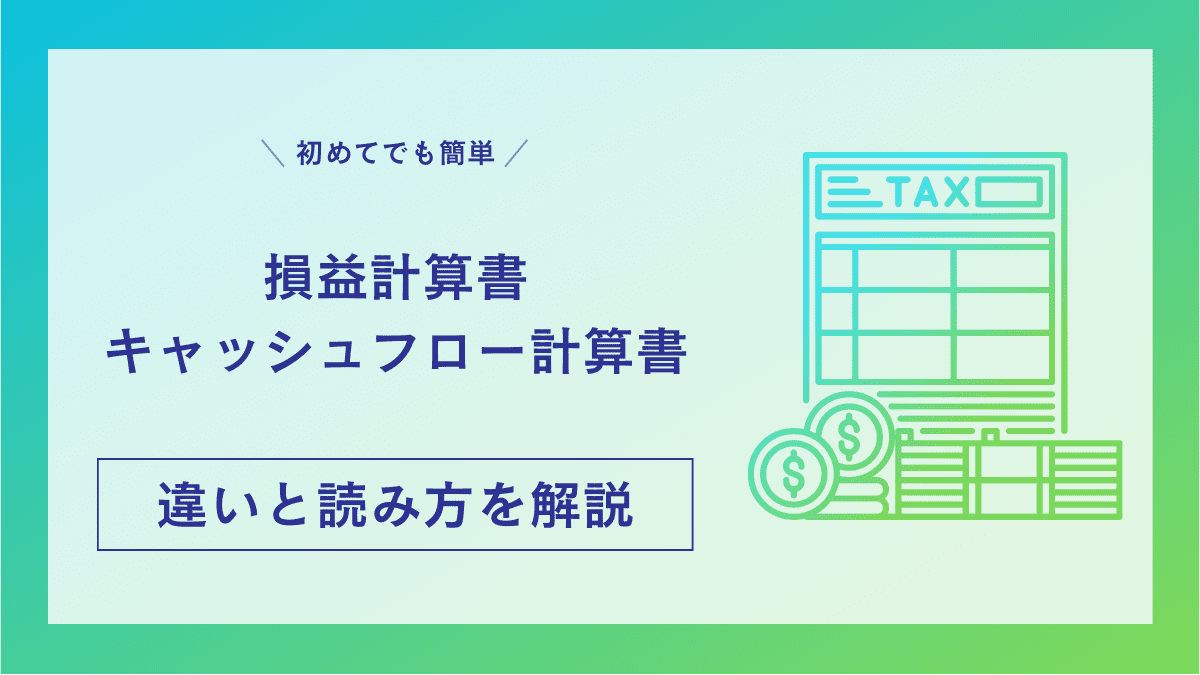「キャッシュフロー計算書と損益計算書の違いは何だろう?」
「キャッシュフロー計算書と損益計算書を見ると何が分かるのだろう?」
このようにお悩みではないでしょうか。キャッシュフロー計算書と損益計算書を知っていても、具体的に何が違うのかわからない方も多いことでしょう。
そこで本記事では、キャッシュフロー計算書と損益計算書の違いを読み方と共に解説し、統合的に分析する方法も解説します。
キャッシュフロー計算書と損益計算書の違いや読み方が分からずに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
キャッシュフロー計算書と損益計算書の概要
初めに、キャッシュフロー計算書と損益計算書の概要を解説していきます。
概要は以下の通りです。
●キャッシュフロー計算書=現金の流れの把握に必要
●損益計算書=会社の収益性を判断するために必要
それぞれ解説していきます。
キャッシュフロー計算書=現金の流れの把握に必要
キャッシュフロー計算書とは、現金の流れを把握するために作成される財務諸表の一つです。
全ての企業や個人事業主に作成義務があるわけではなく、作成義務があるのは上場企業などに限ります。またキャッシュフローとは現金の流れのことで、会計期間中に現金がどれだけ増減したかを表します。
ここで、コンビニを例に挙げて考えてみましょう。
コンビニでは商品を仕入れる場合は代金を支払い、商品を販売した場合は代金を受け取ります。さらにコンビニを経営していく上で、家賃や備品などの経費の支払いもあることでしょう。
このような一連のお金のやり取りが、キャッシュフローです。
貸借対照表を見れば財政状況、損益計算書を見れば期間内の収益が分かりますが、現金の動きが分からないため、キャッシュフロー計算書が必要になります。
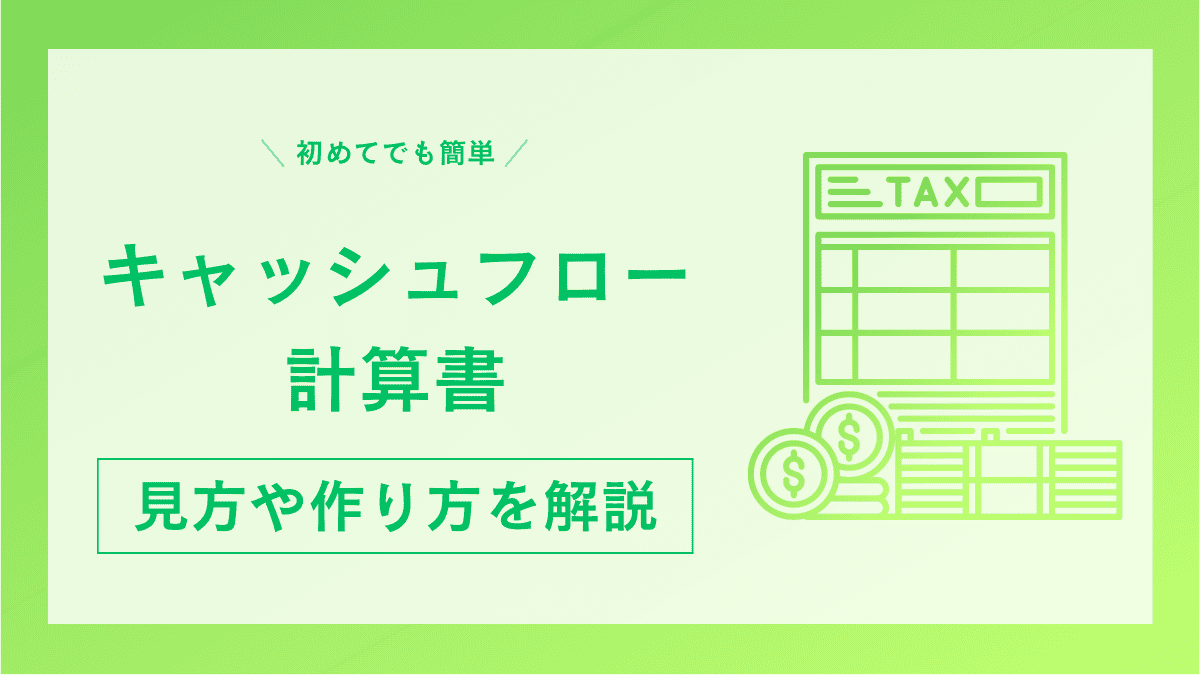
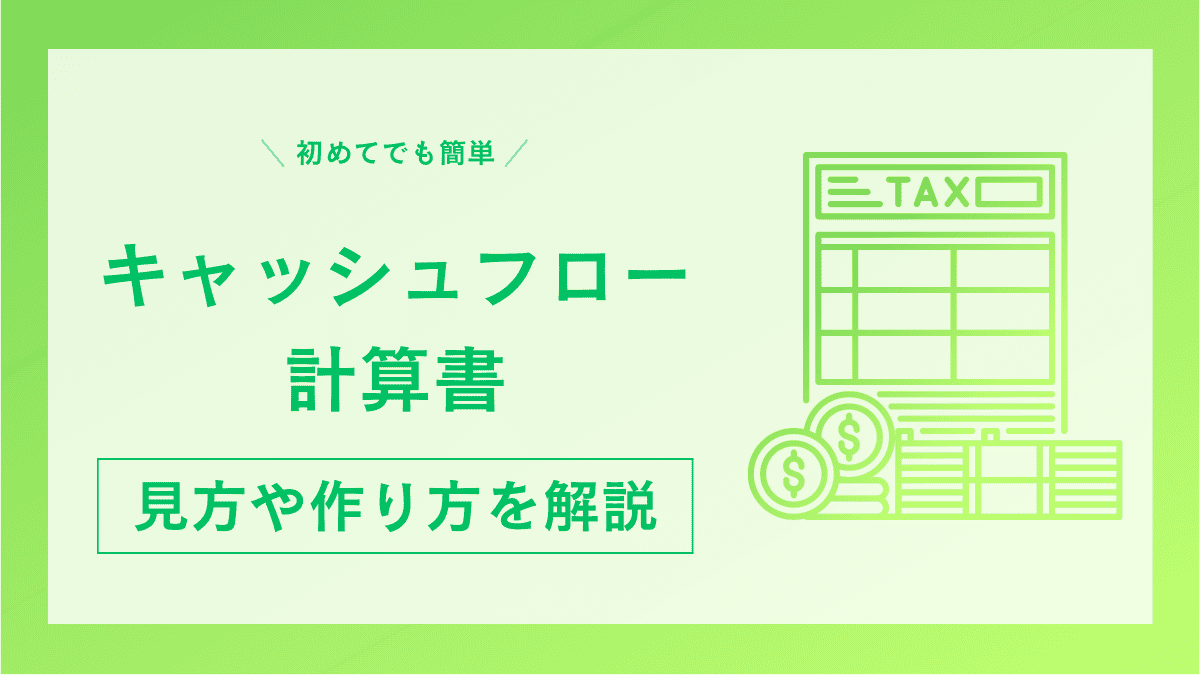
損益計算書=会社の収益性を判断するために必要
損益計算書は、会社の収益性を判断するために必要な財務諸表です。
英語表記では「Profit and Loss Statement」と表されるため、頭文字を取り「PL」とも呼ばれます。
損益計算書は収益・費用・利益の要素で構成されているため、どれだけの収益が計上され、どういった費用を使い、どれくらいの利益が出たかが分かります。
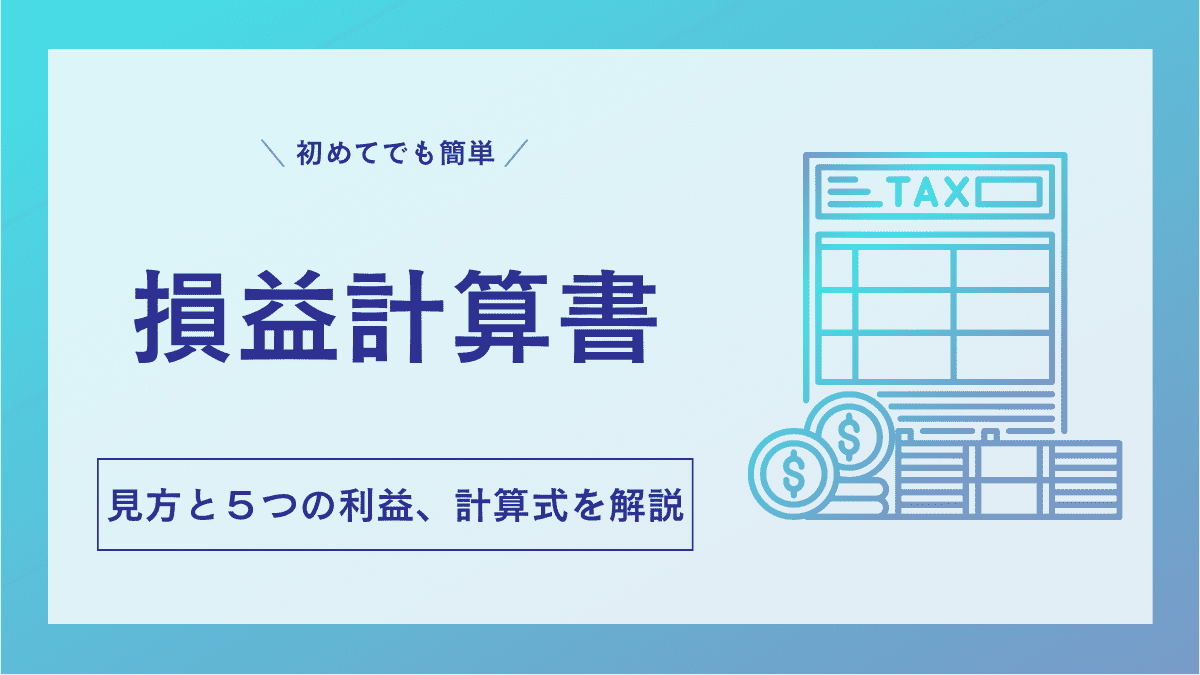
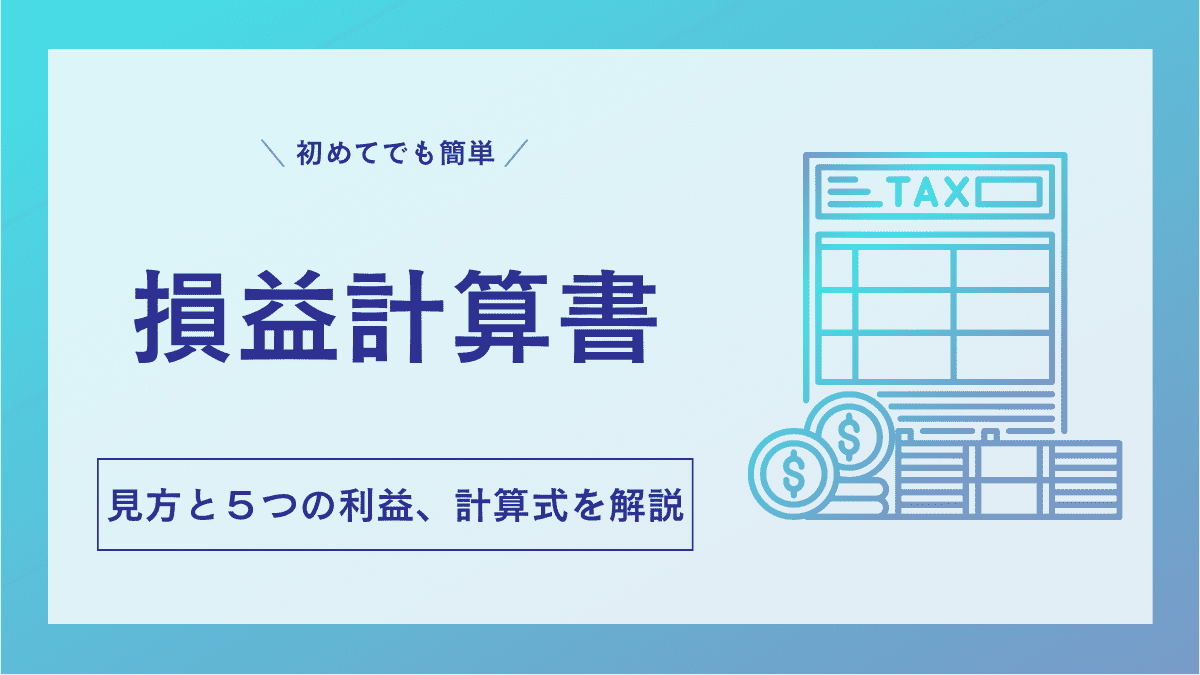
キャッシュフロー計算書の読み方
ここでは、キャッシュフロー計算書の読み方を解説します。
構成から解説しますので、ぜひ参考にしてください。
キャッシュフロー計算書の構成
キャッシュフロー計算書は、以下の3つの区分で構成されています。
| 区分 | 意味 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 売上や仕入代金、経費などの営業活動に関わる収入・支出金額 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 設備の購入や有価証券の売買などの投資活動に関連した収入・支出金額 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 株式の発行や借入、配当などによる資金調達などの財務活動に関わる収入・支出金額 |
また「フリーキャッシュフロー」という言葉も覚えておいてください。
フリーキャッシュフローとは、その名前の通り企業が自由に使える現金のことで、株主への配当や事業への投資などの用途で、自由に使うことができます。
なお一般的に、以下の計算式で求められるため確認しておきましょう。
フリーキャッシュフロー=(営業活動によるキャッシュフロー)ー(投資活動によるキャッシュフロー)
キャッシュフロー計算書に記載される情報の読み方
ここでは、キャッシュフロー計算書を構成する3つの区分から読み取れる情報について、解説していきます。
それぞれの区分ごとに読み取れる情報をまとめた表は、以下の通りです。
| 区分 | 読み取れる情報 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | 本業でどれだけの現金獲得能力があるか |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 本業で利益を獲得するためにどれだけの投資を行ったか |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 営業活動や投資活動で必要な資金をどれだけ調達したか |
3つの区分ごとの意味を覚えることも大切ですが、3つの区分の情報からどのようなことが読み取れるかについても覚えておきましょう。
キャッシュフロー計算書から読み取れる企業の財務状況の評価方法
企業の財務状況を評価するには、キャッシュフロー計算書をどのように読み取れば良いのでしょうか。
まずは、3つに区分したキャッシュフローの符号が、プラスとマイナスのどちらなのかを見ることが重要です。
例えば、以下の企業の財務状況を考えてみましょう。
| 区分 | 符号 | 事象 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | +(プラス) | 本業で現金増 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ー(マイナス) | 設備投資の実施 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | ー(マイナス) | 借入金の返済 |
上記の場合、営業活動によるキャッシュフローの符号がプラスのため、本業の活動により現金が増えたことが分かります。
そして、投資活動によるキャッシュフローの符号がマイナスから分かることは、本業のために設備投資などを行っていること。
さらに、借入金の返済などを進めているために、財務活動によるキャッシュフローの符号はマイナスです。
したがって上記の場合、本業で儲けていて設備投資もでき、さらに銀行へ借入金の返済ができていると読み取れるため、事業が順調に推移している企業という評価ができます。
一方で3つとも逆の符号の場合は、以下のようにまとめられます。
| 区分 | 符号 | 事象 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュフロー | ー(マイナス) | 本業で現金減 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | +(プラス) | 固定資産や有価証券の売却 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | +(プラス) | 借入金増加 |
本業で現金が減ってしまった分を、固定資産や有価証券の売却、また銀行からの借入金で埋め合わせをしていることが予想されますよね。
したがって、この状態が続けば資金繰りが行き詰まることから、事業が順調に進んでいないという評価をされてしまう可能性があります。
ただし、会社を創業したばかりのうちは売上が上がらずに、営業キャッシュフローの符号がマイナスのケースもあることでしょう。
したがって、会社が設立されてからどれくらい経っているかも考慮しながら、企業の財務状況を把握するようにしてください。
損益計算書の読み方
次に、損益計算書の読み方について解説していきます。
ここでも構成から解説しますので、参考にしてください。
損益計算書の構成
損益計算書は、以下の5つの利益で構成されています。
実際に損益計算書に数字をあてはめた例とあわせて、確認してみてください。
| 名称 | 意味 |
|---|---|
| 売上総利益(600) | 売上高から売上原価を差し引いた利益 ※売上(2,000)から売上原価(1,400)を引く |
| 営業利益(200) | 本業の活動で得た利益 ※売上総利益(600)から販売費及び一般管理費(400)を引く |
| 経常利益(180) | 本業以外の活動で得た利益も含んだ、通常の活動で得た利益 ※営業利益(200)から営業外収益・営業外費用(20)を加減する |
| 税引前当期純利益(150) | 法人税等を引く前の利益 ※経常利益(180)から特別収益・特別損失(30)を加減する |
| 当期純利益(100) | 会計期間の最終的な利益 ※税引前当期純利益(150)から法人税等(50)を引く |
・損益計算書の例
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 2,000 |
| 売上原価 | 1,400 |
| 売上総利益 | 600 |
| 販売費及び一般管理費 | 400 |
| 営業利益 | 200 |
| 営業外収益・営業外費用 | 20 |
| 経常利益 | 180 |
| 特別収益・特別損失 | 30 |
| 税引前当期純利益 | 150 |
| 法人税等 | 50 |
| 当期純利益 | 100 |
損益計算書に記載される情報の読み方
損益計算書を読むときは、金額と共に指標も見ると理解しやすくなります。
損益計算書の分析でよく使われる指標は、「売上高総利益率(粗利率)」と「売上高営業利益率」の2つです。
売上高総利益率は、売上高に対して売上総利益(粗利)が占める割合、売上高営業利益率は、売上高に対して営業利益が占める割合をあらわします。
計算方法は下記の通りです。
●売上高総利益率(粗利率)=売上総利益(粗利)÷売上高×100
●売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100
もし売上高総利益率が高ければ、利益率の高い商品やサービスを販売している企業と考えられますよね。
反対に売上高総利益率が低い企業の場合は、利益率が悪いため販売価格や仕入価格が適正でない、または製造業の場合は原材料が高騰しているなどの理由が考えられます。
また営業利益も、売上総利益率同様に営業利益率で見ると、本業の収益性がどの程度か分かります。
損益計算書を読むときは金額だけでなく、割合などの指標もあわせて読むと理解しやすくなることを覚えておきましょう。
損益計算書から読み取れる企業の財務状況の評価方法
損益計算書から財務状況を評価するには、どう読み取ったら良いのでしょうか。
先ほど解説した、売上高営業利益率を例にして考えてみましょう。
実際に先ほど挙げた損益計算書の数字を当てはめて、売上高営業利益率を計算してみます。
営業利益が200で売上高が2,000のため、200÷2,000×100=10%と計算できます。
ここで、経済産業省が公表している業種ごとの売上高営業利益率を確認してみましょう。
| 単位:% | 主要産業の売上高営業利益率 |
|---|---|
| 合計 | 4.3 |
| 製造業 | 5.6 |
| 卸売業 | 2.7 |
| 小売業 | 3.0 |
出典:2022年経済産業省企業活動基本調査速報(2021年度実績)[1]
先ほど計算した売上高営業利益率は10%で、経済産業省が公表している主要産業の全体の売上高営業利益率は4.3%です。
したがって、経済産業省が公表している全体の売上高営業利益率よりも高いことから、本業の収益性が高いことが分かりますよね。
以上のように、会社の財務状況が全体と比べてどのような評価なのかを判断するためにも、金額と共に割合もあわせて確認するようにしましょう。
キャッシュフロー計算書と損益計算書の違い
ここでは、キャッシュフロー計算書と損益計算書の違いを解説していきます。
主な違いは、以下の4つです。
●両者の目的の違い
●構成要素の違い
●記載される情報の違い
●解釈方法の違い
1つずつ解説していきます。
両者の目的の違い
最初に挙げるのが、両者の目的の違いです。
キャッシュフロー計算書は、現金不足にならないように現金の動きを把握するために作成されます。
一方、損益計算書は、会計期間内の会社の収益を把握するために作成されます。
なぜ両方の財務諸表が必要かというと、キャッシュフロー計算書だけではどれくらいの利益が出たか分からず、損益計算書だけでは現金の動きが分からないからです。
したがって、財務分析を行うときにお互いに補完するため、キャッシュフロー計算書と損益計算書の作成が必要になります。
構成要素の違い
キャッシュフロー計算書と損益計算書では、構成要素も違います。
キャッシュフロー計算書は、主に以下の3つで構成されています。
●営業活動によるキャッシュフロー
●投資活動によるキャッシュフロー
●財務活動によるキャッシュフロー
一方損益計算書は、利益だけ見ても以下の5つがあるため、確認しておきましょう。
●売上総利益
●営業利益
●経常利益
●税引前当期純利益
●当期純利益
損益計算書では上記の利益以外にも、売上高や売上原価などの科目もあり、利益がどれだけ出たかを確認するために細かく分類されています。
記載される情報の違い
キャッシュフロー計算書と損益計算書の記載される情報の違いを解説します。
実際に、マルハニチロ株式会社のキャッシュフロー計算書と損益計算書を確認してみましょう。
キャッシュフロー計算書では、それぞれのキャッシュフローの内訳金額が記載されているのに対し、損益計算書では売上高から当期純利益までの金額が記載されています。
目的や構成要素が異なるため、記載される情報が違うことも覚えておきましょう。
解釈方法の違い
解釈方法の違いについても、解説します。
キャッシュフロー計算書は現金主義、損益計算書は発生主義で解釈されます。
現金主義と発生主義の意味は、以下の通りです。
●現金主義:現金がやり取りされた時点で認識する考え方
●発生主義:取引が発生したときに認識する考え方
例えば、売上が上がり売掛金が計上されたときは、売上が「発生」したため損益計算書に売上高が計上されます。
しかし、売上は発生しても、現金の入金はないため、キャッシュフロー計算書には計上されません。
現金主義と発生主義は、キャッシュフロー計算書と損益計算書を考える上で重要な解釈方法のため、覚えておきましょう。
両者を統合的に分析する方法
ここまでキャッシュフロー計算書と損益計算書の読み方や違いを解説してきましたが、ここでは両者を統合的に分析する方法を解説していきます。
両者の情報を統合的に分析するための方法
両者の情報を統合的に分析するためには、損益計算書で利益分析をすると共に、現金の流れを補完するためにキャッシュフロー計算書を活用する方法が効果的といえます。
実はキャッシュフロー計算書は、損益計算書よりも後の2000年3月期から導入された[4] 財務諸表で、当時問題となっていたのが「黒字倒産」です。
黒字倒産とは、損益計算書上は利益が出ている黒字の状態にもかかわらず、支払いに必要な現金がなく、倒産してしまうことです。
そこで利益だけでなく現金の動きも重要視され、キャッシュフロー計算書が導入されました。
現在でも会社の成績を決める主な決算書と言えば損益計算書のため、損益計算書で利益の確認をする必要がありますが、現金が不足すると倒産してしまいます。
したがって、損益計算書で利益の確認をしながら、キャッシュフロー計算書で営業・投資・財務活動のそれぞれのキャッシュフローの状態を確認することが重要です。
両者から読み取れる企業の財務状況の全体像の評価方法
キャッシュフロー計算書と損益計算書から、財務状況を読み取るためにはどうしたら良いのでしょうか。
財務状況を把握する際に、特に重要な営業活動によるキャッシュフローと営業利益について、例を挙げて解説します。
まずは、損益計算書の営業利益を確認してください。
もし営業利益がマイナス、つまり営業損失の場合は損失になってしまった原因を特定することから始めましょう。
営業利益がプラスの場合は、キャッシュフロー計算書の営業活動によるキャッシュフローを確認し、営業利益と営業活動によるキャッシュフローのどちらが大きいかを確認してください。
健全な財務体質の企業は、営業利益より営業活動によるキャッシュフローの方が大きいケースが多いです。
なぜなら、減価償却費は実際には現金が出ていない費用のため、営業活動によるキャッシュフローにプラスされるからです。
したがって、営業活動によるキャッシュフローの方が少なくとも減価償却費の金額分だけ大きくなるため、営業利益よりも大きくなります。
反対に営業活動によるキャッシュフローよりも営業利益の方が大きい場合は、不当に損益額を調整していないかを指摘される恐れがあるため、要因を突き止めることが大切です。
まとめ
本記事では、キャッシュフロー計算書と損益計算書の違いについて解説しました。
キャッシュフロー計算書は現金の流れを把握するために作られ、損益計算書は会社の収益性を判断するために作成されています。
さらに構成要素、記載される情報、解釈方法などの違いもあります。
また、両者から現金の流れと利益を把握して分析しないと、黒字倒産をしてしまう恐れがあるため、両者を統合的に分析することの重要性についても解説しました。
本記事では、特にキャッシュフロー計算書の営業活動によるキャッシュフローと、損益計算書の営業利益を比べる方法を解説しましたので、ぜひ参考にしてください。