損益計算書は収益や利益などを把握できるため、飲食店の経営のために重要な決算書類です。
しかし、飲食店を経営している人の中には、損益計算書に不慣れで見方がわからない人が多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では飲食店の損益計算書の見方や作り方を解説していきます。
さらに、損益計算書の3つの作成方法を解説し、テンプレートも紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
そもそも損益計算書(PL)とは?
損益計算書(PL)とは、一定期間の経営成績を収益・費用・利益の面から把握できる決算書類です。
飲食店がどれだけ儲けているか、もしくはどれだけ損を出しているかを損益計算書から把握できます。
損益計算書を構成する収益・費用・利益の3つの項目の説明と、項目ごとの飲食店の例を挙げると、下記の通りとなります。
● 収益:どれだけの売上があったか。例)料理や飲み物の代金、デリバリーの料金など
● 費用:どれだけの費用がかかったか。例)料理や飲み物の費用、人件費など
● 利益:どれだけの利益が残っているか
上記のように、損益計算書を構成する3つの項目と飲食店の例をあわせて理解すると、わかりやすいのではないでしょうか。
なお、損益計算書は英語で「Profit and Loss Statement」と表記されるため、頭文字を取り「P/L(ピーエル)」と呼ばれることも覚えておくとよいでしょう。
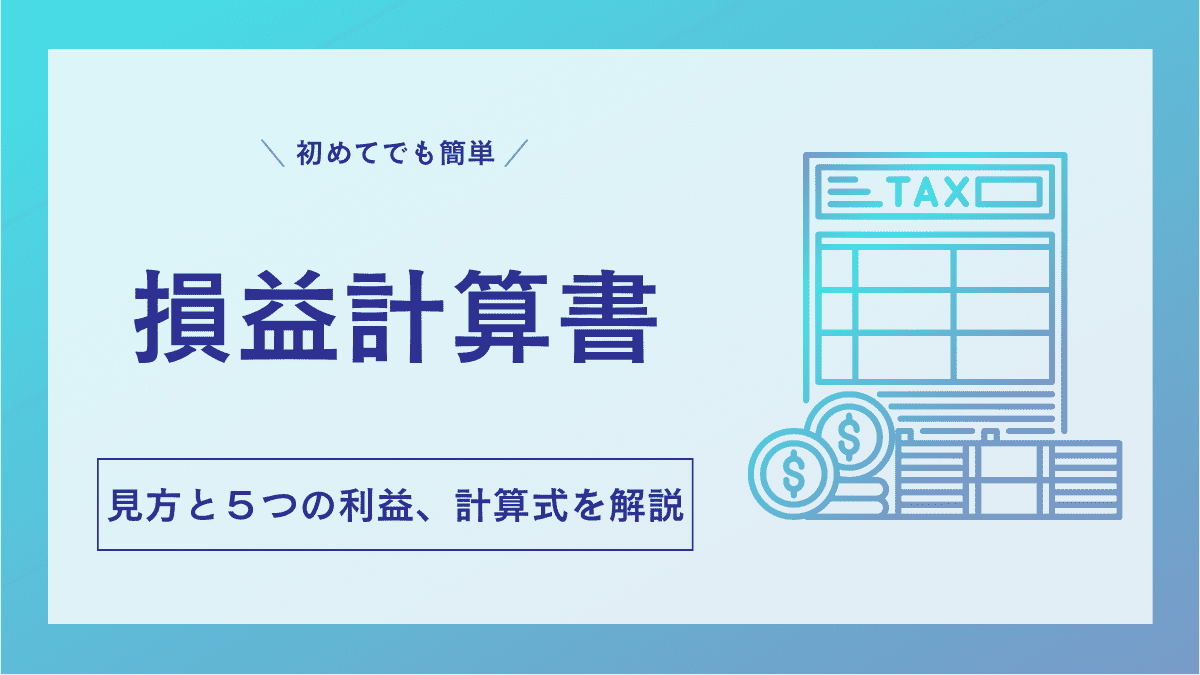
飲食店で損益計算書を作る理由
前の章で解説した通り、損益計算書は一定期間の経営成績がわかる決算書類です。
それでは、飲食店で損益計算書を作る理由は、何が挙げられるでしょうか?
主に下記の3つが、飲食店で損益計算書を作る理由となります。
● 経営状況を数字で把握するため
● 競合他社と比較するため
● 金融機関や取引先に信頼してもらうため
1つずつ解説していきます。
経営状況を数字で把握するため
1つ目は、経営状況を数字で把握するためです。
損益計算書を作成すれば、料理や飲み物の売上金額や材料費、さらに人件費や水道光熱費などの金額がわかり、どれだけの利益もしくは損失が出ているのかがわかります。
もし損失が出ていることがわかったら、改善計画を立てられるため、経営状況を把握することは重要といえるでしょう。
競合他社と比較するため
2つ目は、競合他社と比較するためです。
損益計算書は表示する項目が決まっているため、自社と競合他社を同じ基準で比較できます。
単純に金額同士の比較ができるのはもちろんのこと、売上高に占める営業利益の割合を示す、売上高営業利益率などの指標を用いての比較も可能です。
金融機関や取引先に信頼してもらうため
3つ目は、金融機関や取引先に信頼してもらうためです。
損益計算書を作成して財務面で健全なことをアピールできれば、金融機関や取引先に信頼してもらえることでしょう。
もし損益計算書がなければ判断する材料がないため、金融機関や取引先が自社に融資をして良いのか判断できず、資金調達が難しくなってしまいます。
財政状況を表す貸借対照表もあわせて作成することで、金融機関や取引先に信頼してもらえるようにしましょう。
飲食店の損益計算書の項目一覧
ここまで損益計算書の定義や作る理由を解説しましたが、「飲食店の損益計算書」のイメージをしづらい人もいるかもしれません。
そこで、ここでは飲食店の損益計算書の項目一覧を解説していきます。
飲食店の損益計算書の項目一覧は下記の通りなので、確認してみてください。
| 項目 | 上段:意味 下段:飲食店の例 |
|---|---|
| 売上 | 本業の商品やサービスの売上のこと。 例)飲食物の代金、デリバリーの料金など。 |
| 売上原価 | 売り上げた商品やサービスの仕入・製造費用のこと。 例)飲食物の材料費など。 |
| 販売費及び一般管理費 | 商品やサービスの販売や管理をするための費用のこと。 例)広告宣伝費、人件費、水道光熱費など。 |
| 営業外収益 | 本業以外で経常的に発生する利益のこと。 例)受取配当金や受取利息など。 |
| 営業外費用 | 本業以外で経常的に発生する費用のこと。 例)借入金の支払利息など。 |
| 特別利益 | 臨時的に発生した利益のこと。 例)飲食設備の売却益など。 |
| 特別損失 | 臨時的に発生した費用のこと。 例)飲食設備の売却損、災害の影響による損失など。 |
| 法人税等 | 利益にかかる税金のこと。 例)法人税、住民税、事業税など。 |
飲食店特有の損益計算書の勘定科目
損益計算書を作成する際に、飲食店特有の勘定科目として衛生費・保安費・燃料費の3つがあります。
それぞれの意味は下記の通りのため、覚えておきましょう。
| 勘定科目 | 意味 |
|---|---|
| 衛生費 | 店舗の清掃代や害虫駆除代など、飲食店の店舗の衛生のためにかかる費用のこと。 |
| 保安費 | 飲食店の店舗を警備・保安するためにかかる費用のこと。 |
| 燃料費 | 木炭・練炭・ガスなどの調理用の燃料にかかる費用のこと。 |
飲食店の損益計算書の見方
飲食店の損益計算書の項目一覧は前の章で解説した通りですが、損益計算書で表示される5つの利益の見方についても理解する必要があります。
そこで、ここでは飲食店の損益計算書の見方を理解するために、下記の5つの利益を解説していきます。
● 売上総利益(粗利)
● 営業利益
● 経常利益
● 税引前当期純利益
● 当期純利益
1つずつ解説していきますので、確認していきましょう。
売上総利益(粗利)
損益計算書を上から順番に見ていったときに、一番初めに表示されているのが売上総利益(粗利)です。
売上総利益は、売上高から売上原価を引いた利益のことで、計算式で表すと下記の通りです。
売上総利益=売上高ー売上原価
飲食店の場合、飲食物の代金から飲食物の材料費などを引くと売上総利益になるため、売上総利益は飲食物の材料費を除いた儲けがいくらかがわかります。
営業利益
営業利益は、本業の儲けを表す利益のことで、計算式は下記の通りです。
営業利益=売上総利益ー販売費及び一般管理費
飲食物の利益を示す売上総利益から、人件費や水道光熱費などの販売費及び一般管理費を引くため、営業利益は飲食店の本業である飲食サービスの儲けを把握できます。
もし、売上総利益が大きく営業利益が小さい場合は、人件費や水道光熱費、また店舗の家賃がかかり過ぎている可能性があるため確認するとよいでしょう。
営業利益は、飲食の本業でどれだけ稼げているかがわかる利益のため、確実に把握しておくべき利益といえます。
経常利益
経常利益は、通常の活動で出た利益を表し、計算式は下記の通りです。
経常利益=営業利益+営業外収益ー営業外費用
飲食の本業以外の配当金や、金融機関などへの借入金の利息などが経常利益に含まれます。
営業利益が競合他社と比べて同等にもかかわらず、経常利益の金額が小さい場合は、金融機関からの借入金などが大きすぎる可能性があることに注意をしましょう。
税引前当期純利益
税引前当期純利益は、飲食店の全ての活動で得た利益を表し、計算式は下記の通りです。
税引前当期純利益=経常利益+特別利益ー特別損失
特別利益や特別損失は、臨時的に発生した利益や損失のことで、飲食設備の売却益や売却損などが該当します。
税引前当期純利益は、臨時的に発生した損益も含めた全ての利益と覚えておくとよいでしょう。
当期純利益
法人税などの税金を引かれ、最終的に飲食店に残る利益を表し、計算式は下記の通りです。
当期純利益=税引前当期純利益ー法人税等
最終的に残る利益のため、配当金の原資になることも覚えておきましょう。
損益計算書を飲食店経営に活かす4つの方法
前の章までで、損益計算書の項目や見方を解説してきました。
ここでは、損益計算書を飲食店経営に活かす4つの方法を解説していきます。
● 売上高営業利益率を計算する
● 損益分岐点売上高を計算する
● 目標利益達成売上高を計算する
● FL率を計算する
損益計算書を飲食店経営に活かすために、1つずつ確認していきましょう。
売上高営業利益率を計算する
売上高営業利益率とは、売上高に占める営業利益の割合のことで、計算式は下記の通りです。
売上高営業利益率(%)=営業利益÷売上高×100%
飲食店の場合、5%~10%が目安で、10%を超えると優良な経営をしていると判断されます。
もし目安以下の場合は、材料費の高騰や、人件費・広告宣伝費の使いすぎなどがないかの点検をしてみましょう。
損益分岐点売上高を計算する
損益分岐点売上高は、売上と費用が同じになる売上高のことで、計算式は下記の通りです。
損益分岐点売上高=固定費÷{1ー(変動費÷売上高)}
計算式に変動費と固定費がありますが、それぞれの定義と飲食店の例を下記にまとめたのでご確認ください。
| 費用の種類 | 上段:意味 下段:飲食店の例 |
|---|---|
| 変動費 | 売上に比例して増加する費用のこと。 例)飲食物の材料費、水道光熱費など。 |
| 固定費 | 売上に関係なく一定に発生する費用のこと。 例)店舗の家賃、人件費、減価償却費など。 |
損益分岐点売上高を求めるためには、勘定科目ごとに変動費・固定費に分けて金額を把握し、計算式に当てはめる必要があります。
例えば、売上高100万円、変動費40万円、固定費30万円のときの損益分岐点売上は、下記の計算式の通り、50万円となります。
損益分岐点売上高(50万円)=固定費(30万円)÷{1ー(変動費(40万円)÷売上高(100万円))}
さらに、より具体的に損益分岐点売上高を把握するためには、求めた損益分岐点売上高を販売単価と販売数量に分け、販売すべき数量を算出するとよいでしょう。
目標利益達成売上高を計算する
売上と費用が同じになる売上高を求める、損益分岐点売上高の算出ができたら、目標利益達成売上高を計算してみましょう。
目標利益達成売上高とは、目標とする利益をあげるための売上高のことで、計算式は下記の通りです。
目標利益達成売上高=(目標利益+固定費)÷{1ー(変動費÷売上高)}
損益分岐点売上高の計算で使用した例と同様に、売上高100万円、変動費40万円、固定費30万円のケースを想定し、目標利益を90万円で設定して計算してみましょう。
上記のケースを計算式に当てはめると下記のようになり、目標利益達成売上高は200万円になります。
目標利益達成売上高(200万円)=(目標利益(90万円)+固定費(30万円))÷{1ー(変動費(40万円)÷売上高(100万円))}
目標利益達成売上高についても、算出された売上高から販売単価と販売数量を算出しておくとよいでしょう。
FL率を計算する
FL率とは、売上高のうち「FLコスト」が占める割合のことです。
FLコストは、食材費(Food)と人件費(Labor)の合計金額のことで、それぞれの頭文字をとって名付けられています。
飲食店の経営に関する特有の指標のため、覚えておきましょう。
FL率の計算式は下記の通りです。
FL率(%)=(食材費+人件費)÷売上高×100%
損益計算書の売上総利益は大事な項目ですが、飲食店の場合は飲食物の材料費と人件費の占める割合が大きいため、経営指標としてFL率がよく使われます。
また、一般的にFL率は50%以下であれば良いとされています。
もしFL比率が50%より大きい場合は、材料費や人件費のコストがかさんでいると判断できるため、材料費や人件費を点検した方がよいといえるでしょう。
飲食店の損益計算書の3つの作成方法
飲食店の損益計算書を作成する際に全て手書きで行う方法もありますが、効率的でなく間違うリスクもあるため、おすすめの方法とはいえません。
そこで、ここでは飲食店の損益計算書の3つの作成方法を解説していきます。
● エクセルで作成する
● 会計ソフトを使用する
● 経理アウトソーシングに任せる
1つずつ解説しますので、自社にあった方法を探してみてください。
エクセルで作成する
1つ目は、エクセルで作成する方法です。
ツールや外注を利用しない場合におすすめの方法で、手作業よりも入力が簡単にできるため、効率的に損益計算書を作成できることがメリットに挙げられます。
デメリットは、普段からパソコンに使い慣れていないと、エクセルの扱いが難しいことです。
エクセルを使用する場合は、自分で計算式を組んでテンプレートなどを作って作業を進める必要がありますが、パソコンを使い慣れていない人には難しく感じるかもしれません。
そこで、もしエクセルで損益計算書を作成したいものの、テンプレートを作れない場合は、下記のURLからテンプレートを取得してみてください。
株式会社マネーフォワード(【税理士監修】損益計算書飲食店テンプレート(エクセル))
株式会社マネーフォワードが提供する、飲食店専用の損益計算書のエクセルテンプレートのため、参考にしてみてください。
会計ソフトを使用する
2つ目が、会計ソフトを使用する方法です。
メリットは、指定された箇所に入力すれば簡単に仕訳が作成でき、自動で集計して帳簿を作成してくれるため、効率的に作成を進められることが挙げられます。
デメリットは、会計ソフト特有の操作を覚えなければならないことや、運用コストがかかることです。
一度使ってしまえば次第に慣れ、コスト以上の効果を得られる可能性があるため、気になる人は試してみてもよいでしょう。
経理アウトソーシングに任せる
3つ目が、経理アウトソーシングに任せる方法です。
メリットは、経理専門の会社に依頼するため、正確な損益計算書を作成してくれる点です。
また、損益計算書を作成する時間が省けるため、本業の飲食業に集中できることも挙げられます。
一方、デメリットはコストがかかることです。
自分でエクセルで作成すればコストがかからないため、デメリットの一つといえるでしょう。
さらに、外注してしまうため自社に損益計算書を作成するノウハウがたまらないことも、デメリットの一つです。
まとめ
本記事では、飲食店の損益計算書について詳しく解説しました。
飲食店で損益計算書を作る理由は、下記の3点です。
● 経営状況を数字で把握するため
● 競合他社と比較するため
● 金融機関や取引先に信頼してもらうため
飲食店の経営を行う上で、上記の理由から損益計算書の作成が必要になることを覚えておきましょう。
また、損益計算書を飲食店経営に活かす4つの方法は、下記の通りです。
● 売上高営業利益率を計算する
● 損益分岐点売上高を計算する
● 目標利益達成売上高を計算する
● FL率を計算する
特に、FL率は飲食業界特有の計算式のため、理解しておきましょう。
さらに、飲食店の損益計算書の3つの作成方法は、下記の3つです。
● エクセルで作成する
● 会計ソフトを使用する
● 経理アウトソーシングに任せる
3つの方法のメリットとデメリットを参考にしていただき、自社の状況を考慮しながら、どの方法で損益計算書を作成するかを検討してみてください


