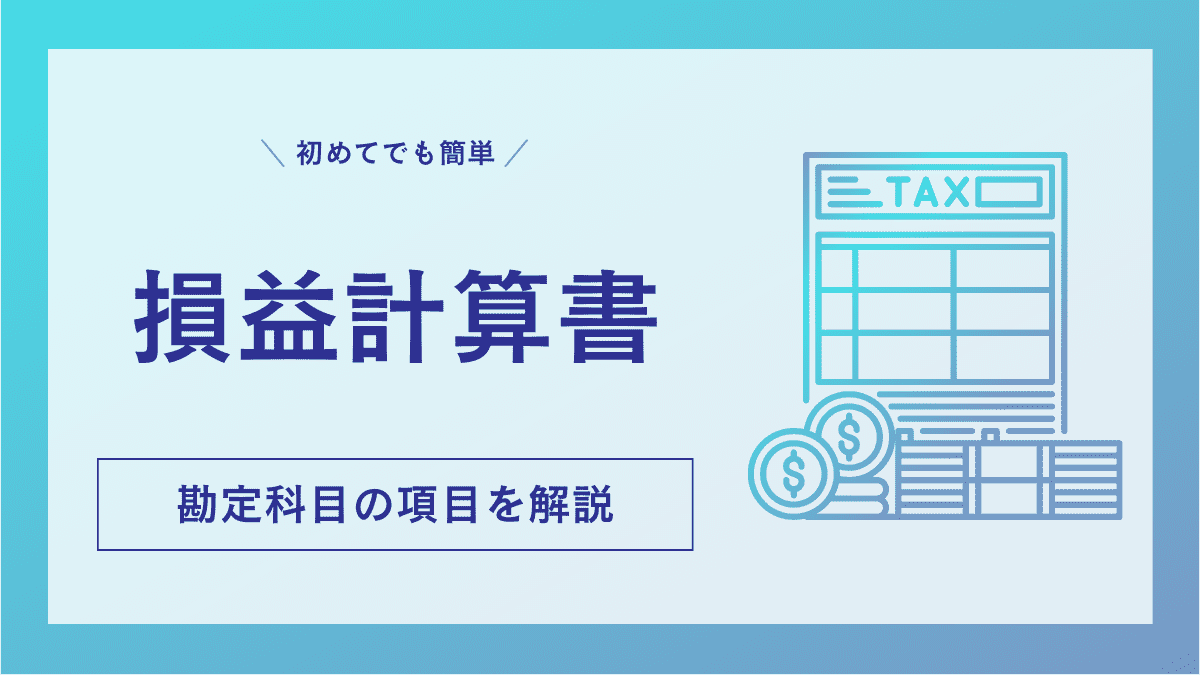損益計算書などで使われる勘定科目は、さまざまな種類があります。
さらに、似た名称の勘定科目もあるため、勘定科目を1つずつ覚えるのは大変です。
また、勘定科目を調べようと思っても1つずつ調べなくてはいけないため、どうしても時間がかかってしまいますよね。
そこで、この記事では勘定科目一覧を項目ごとに徹底解説していきます。
さらに勘定科目を用いる理由や、注意点も解説しますので、損益計算書の勘定科目でお悩みの人はぜひ最後までお読みください。
損益計算書は3つの項目で構成される
損益計算書は、一定期間の企業の経営成績が分かる決算書類で、3つの項目で構成されています。
3つの項目とは、収益・費用・利益のことで、考え方は下記の通りです。
● 収益:一定期間内であげた売上
● 費用:一定期間内で使用した費用
● 利益:収益から費用を差し引いた儲け
損益計算書を見る際にいろいろな項目がありますが、上記3つの項目で構成されていることを覚えておくとよいでしょう。
分析に重要な勘定科目である「5つの利益」
損益計算書では5つの利益が段階的に表示されており、分析をする際に5つの利益が重要な役割を果たします。
5つの利益をまとめた表は、下記の通りです。
損益計算書を正しく分析するために、5つの利益が意味していることを理解しましょう。
| 利益 | 内容 |
|---|---|
| 売上総利益 | 売上高から売上原価を引くことで求められる利益。粗利(あらり)とも呼ばれる。英語表記が「Gross Profit」のため、頭文字を取り「GP(ジーピー)」と呼ばれることもある。 計算式は下記の通り。売上総利益(粗利)=売上高ー売上原価 |
| 営業利益 | 売上総利益から販売費及び一般管理費を引くことで求められ、本業で稼いだ利益を表す。英語表記が「Operating Profit」のため、頭文字を取り「OP(ジーピー)」と呼ばれることもある。 計算式は下記の通り。営業利益=売上総利益ー販売費及び一般管理費 |
| 経常利益 | 営業利益に営業外収益を足し、営業外費用を引くことで求められ、通常の企業活動で稼いだ利益を表す。「経常(けいつね)」とも呼ばれる。 計算式は下記の通り。経常利益=営業利益+営業外収益ー営業外費用 |
| 税引前当期純利益 | 経常利益に特別収益を足し、特別損失を引くことで求められ、企業が全ての活動により稼いだ利益を表す。 計算式は下記の通り。税引前当期純利益=経常利益+特別収益ー特別損失 |
| 当期純利益 | 税引前当期純利益から法人税等を引くことで求められ、最終的に企業に残る利益を表す。 計算式は下記の通り。当期純利益=税引前当期純利益ー法人税等 |
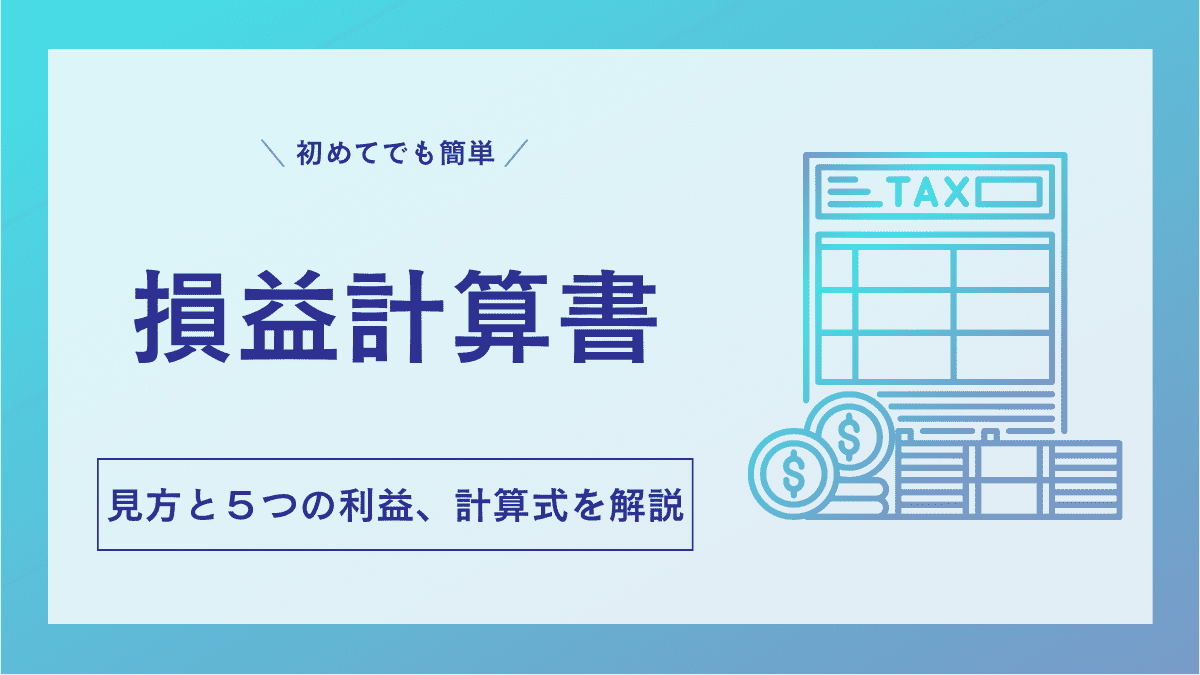
損益計算書の勘定科目一覧
ここまで損益計算書は3つの項目で構成され、5つの利益があることを解説しましたが、損益計算書の勘定科目には、どういったものがあるのでしょうか?
そこで、下記の項目ごとに細かく解説していきます。
● 売上高
● 売上原価
● 販売費及び一般管理費
● 営業外収益
● 営業外費用
● 特別利益
● 特別損失
● 法人税等
各企業で一般的に使われる勘定科目を解説していくので、ぜひ参考にしてください。
売上高
売上高は、本業の商品やサービスなどを提供したことにより得た、売上金額の合計のことです。
売上高に計上される一般的な勘定科目は、下記の通りです。
● 売上値引き:商品の品質不良などにより、売上金額から控除される値引金額
● 売上返品:品質不良などで販売した商品の返品を受けた際に、返品代金を処理する勘定科目
● 売上割戻し:期間内に多額または大量の購入を行った得意先に、商品代金の一部を戻す際に使用する勘定科目
売上原価
売上原価は、当期に売り上げた商品・サービスなどにかかった仕入金額や製造費用のことです。
売上原価を計上するために用いられる勘定科目は、下記の通りです。
● 期首商品棚卸高:前期に在庫として残り、当期に繰り越された商品
● 当期仕入高:当期の売上のために使われた仕入費用
● 仕入値引:売上品の品質不良や破損などで仕入高から控除される金額
● 仕入返品:品質不良などで購入した商品を返品する際に、買掛金の減額や払戻金を仕入高から控除するために使用する勘定科目
● 仕入割戻し:期間内に多額または大量の購入を行った仕入先から、代金の一部が返還される際に使用する勘定科目
● 期末商品棚卸高:当期で販売できず期末に在庫として残った商品で、来期以降に販売するために繰り越される勘定科目
販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費は、本業の活動を行う中で発生した、販売に関わる費用や一般管理業務の費用のことです。
販売費及び一般管理費に計上される一般的な勘定科目は、下記の通りです。
● 役員報酬:取締役・監査役の職務の対価として支給される報酬金額
● 役員賞与:取締役・監査役の職務の対価として支給される報酬金額のなかで賞与分にあたる金額
● 役員退職金:取締役・監査役などの役員が退職した際に支給される退職慰労金
● 給与手当:従業員の給与や手当などの金額
● 賞与:従業員に臨時で支給される賃金(ボーナス)。一般的には夏と冬の年二回支給される。
● 退職金:退職までの勤務の対価として、退職時に従業員へ支給される金額
● 法定福利費:従業員の健康保険料や労働保険料など納付が定められるもののうち、会社が負担する金額
● 福利厚生費:給与手当などとは別に従業員従業員に支給されるもので、結婚や出産の祝い金、また香典代や病気の見舞金などの社会通念上相当と認められる金額
● 雑給:アルバイトやパートタイマーなど臨時で雇用している人に支払う給与や手当などの金額
● 外注費:業務委託契約などで業務を依頼した他企業や個人事業主に支払う費用
● 販売手数料:商品・サービスを販売した代理店などに手数料として支払う費用
● 荷造運賃:荷造費や梱包材料費など、商品を出荷する際に発生する費用
● 広告宣伝費:自社商品やサービスを不特定多数の人に向けて宣伝する際にかかった費用
● 旅費交通費:従業員が業務をするために移動した際にかかった費用のことで、電車代やタクシー代、宿泊費などの費用
● 会議費:取引先や社内の打ち合わせなど、業務で必要な会議や打ち合わせを実施する際にかかる費用
● 交際費:得意先などに対する接待や慰安、贈答などでかかる費用
● 水道光熱費:企業が活動するために使用した、上下水道料金やガス代、電気代などの費用
● 通信費:企業が活動するために使用した、電話料金や郵便代、インターネット代などの費用
● 消耗品費(事務用品費):企業が活動するために使用した文房具やコピー用紙、包装紙など、短期間で消耗されるものの費用
● 租税公課:法人税、消費税、住民税、事業税以外の租税公課の金額。例えば自動車税や固定資産税、印紙税や不動産取得税など
● 寄付金:見返りを求めずに、特定の組織や団体に無償で贈与する金銭のこと
● 修繕費:機械装置や工具器具備品などの固定資産を原状回復させるために修繕をした費用
● 地代家賃:事務所などの建物や駐車場、倉庫などの使用料
● 賃借料:土地・建物以外の機械などの資産を借りるための費用
● 減価償却費:固定資産の取得価額を、定率法や定額法などにより耐用年数にあわせて配分し、期間ごとに計上する費用
● 繰延資産償却費:繰延資産として資産を計上した場合に、償却期間の決算時に償却して費用化するときに使用する勘定科目
● 保険料:火災保険や自動車保険、生命保険など、保険会社と結んだ契約に応じて支払う費用
● 支払手数料:銀行の振込手数料や不動産売買の仲介手数料などで支払った費用
● 支払報酬料:弁護士や税理士、また司法書士やイラストレーターなどの専門家に支払った顧問料などの報酬
● 諸会費:会社の活動に関係する業界団体や商工会議所、自治体などの会費として支払った費用
● 新聞図書費:新聞や書籍、雑誌などを購入するために支払った費用
● 研究開発費:新しい商品やサービスの開発や新しい技術の研究などにかかった費用
● 研修費:従業員が業務上必要な知識や技術を身に付けるために参加した、研修会や講習会、セミナーなどに参加した費用
● リース料:リース契約を結んで使用しているパソコンやコピー機などのリース料としてかかった費用
● 貸倒損失:取引先の倒産などで回収できなくなった売掛金・貸付金などの債権の金額
● 貸倒引当金繰入額:売掛金などの債権が、貸倒により回収不能になる場合に備えて見積もられた金額
● 賞与引当金繰入額:翌期に従業員に支給される賞与のうち、当期に負担すべき金額を計上するときに使用する勘定科目
● 退職給付費用:将来従業員の退職時に支払う退職金のうち、当期に負担する金額を見積もり、費用計上する際に使用する勘定科目
● 雑費:上記までに解説した勘定科目に含まれない費用や、少額で金額が重要でないものを計上するときに使用する勘定科目
営業外収益
営業外収益は、企業の本業以外の活動で経常的に発生する収益のことです。
営業外収益に計上される一般的な勘定科目は、下記の通りです。
● 受取利息:預金、貯金、有価証券などから得られる利息
● 受取配当金:他の法人から受ける剰余金の配当や利益の配当、また剰余金の分配などの金額
● 仕入割引:買掛金を支払期日よりも早期に支払うことで受けた一定の割引金額
● 為替差益:為替が変動したことにより得た利益
● 有価証券売却益:有価証券を売却したことで得た利益
● 有価証券評価益:売買目的有価証券を時価評価したことにより発生した評価益
● 貸倒引当金戻入益:貸倒引当金を戻し入れする(減らす)場合に計上する勘定科目
● 賞与引当金戻入益:計上していた賞与引当金よりも賞与の実際の支給額が小さい場合の差額を計上する勘定科目
● 退職給与引当金戻入益:退職給付引当金を取り崩したときに使用する勘定科目
● 雑収入:本業以外の収益であり、上記の勘定科目に該当しない内容で、金額が小さく重要性が低いときに使用する勘定科目
営業外費用
営業外費用は、企業の本業以外の活動で経常的に発生する費用のことです。
営業外費用に計上される一般的な勘定科目は、下記の通りです。
● 支払利息:借入金や社債などで発生した利息
● 売上割引:売掛金を期日よりも早期に受け取ったことで行った一定の割引金額
● 手形売却損:手形割引を行った際に差し引かれる、手形の満期日までの利息相当額
● 為替差損:為替が変動したことにより発生した損失
● 有価証券売却損:有価証券を売却したことにより発生した損失
● 有価証券評価損:売買目的有価証券を時価評価したことにより発生した評価損
● 投資有価証券売却損:売買以外の目的の有価証券を売却したことで発生した損失
● 雑損失:本業以外の費用であり、上記の勘定科目に該当しない内容で、金額が小さく重要性が低いときに使用する勘定科目
特別利益
特別利益は、企業の事業内容と直接関わりがなく、臨時的に発生した利益のことです。
特別利益に計上される一般的な勘定科目は、下記の通りです。
● 固定資産売却益:土地や機械装置などの固定資産を売却した際に得た利益
● 償却債権取立益:過去に貸倒処理をした債権を回収したときの回収金額
● 保険差益:火災などを受けて損害保険会社から受けた保険金額が、災害による損失金額よりも大きいとき、保険金額を超える金額分を計上する勘定科目
● 前期損益修正益:過年度分の経理処理の誤りを修正したことで発生した利益
● 投資有価証券売却益: 売買以外の目的の有価証券を売却したことで発生した利益
特別損失
特別損失は、企業の事業内容と直接関わりがなく、臨時的に発生した損失のことです。
特別損失に計上される一般的な勘定科目は、下記の通りです。
● 固定資産売却損:土地や機械装置などの固定資産を売却した際に発生した損失
● 固定資産除却損:固定資産を廃棄したときに発生した損失
● 災害損失:火災や災害などにより損失した棚卸資産や固定資産や、災害の後処理で発生した費用などを計上する勘定科目
● 前期損益修正損:過年度分の経理処理の誤りを修正したことで発生した損失
法人税等
法人税等は、法人税や法人住民税など、法人が納める税金のことです。
法人税等に含まれる勘定科目は、下記の通りです。
● 法人税、住民税及び事業税:当期の所得に対して課せられた税金
● 法人税等調整額:会計上の利益と税務上の課税所得の差を解消するために使われる勘定科目
勘定科目を用いる4つの理由
ここまで見てきたように、勘定科目にはさまざまな種類があり、会計の処理を行う際は、適切な勘定科目を用いる必要があります。
それでは、なぜ損益計算書に勘定科目を用いるのでしょうか?
損益計算書に勘定科目を用いる理由は、下記の4つです。
● 仕訳をして決算書類を作成するため
● みんなが同じ方法で帳簿作成と分析を可能にするため
● お金の流れを把握し経営改善するため
● 税金の計算をするため
1つずつ解説していきますので、勘定科目の理解を深めていきましょう。
仕訳をして決算書類を作成するため
日々の取引を記録する際に仕訳をしていきますが、仕訳には勘定科目が必要です。
仕訳は、借方・貸方に勘定科目と金額をそれぞれ記載する作業のことで、仕訳をもとに損益計算書などの決算書類を作成していきます。
したがって、勘定科目が記載された仕訳がないと株主など企業に関わる人に決算書類を報告できないため、勘定科目は重要な役割を持っているといえます。
みんなが同じ方法で帳簿作成と分析を可能にするため
勘定科目の内容が決められていれば、みんなが同じ方法で帳簿を作成でき、さらに過去の帳簿と当期の帳簿を正しく分析できます。
しかし、もし勘定科目の内容が決められておらず、帳簿の作成者が好き勝手に勘定科目を使用してしまうと、毎回帳簿の前提が異なってしまうため、正しい分析ができません。
決められた勘定科目があれば、みんなが同じ考え方で帳簿を作成でき、分析も可能にできることも、勘定科目を用いる理由の一つです。
お金の流れを把握し経営改善するため
勘定科目を用いて損益計算書を作成すれば、売上高が前期と比べてどうだったのか、また販売費及び一般管理費を使い過ぎていないかなど、お金の流れの把握ができます。
そして、損益計算書でお金の流れを把握すれば、今後売上を伸ばすべきなのか、それとも経費を抑制すべきなのかなどの経営上の改善点が見えてきます。
また、損益計算書を公表すれば利害関係者などのステークホルダーでも分析が可能です。
外部でも企業の経営が適切に行われているかを確認して指摘できることからも、勘定科目は正しく経営をしていくために重要な役割を持っているといえるでしょう。
税金の計算をするため
税金の勘定科目の中に法人税、住民税及び事業税があり、金額を算出する際は会計上の利益と税務上の課税所得を調整する必要があります。
例えば、交際費の勘定科目で計上すると、会計上は費用にできますが、税務上は原則損金不算入、つまり費用にできません。
そこで勘定科目を用いれば、勘定科目ごとに課税対象なのかどうかはっきりと区別できるため、税金の計算を正しく行えます。
したがって、税金計算の面でも勘定科目が重要な役割を果たしているといえます。
勘定科目を用いる時の3つの注意点
勘定科目を用いれば、決算書類を作成できて、正しく税金計算ができるなどたくさんのメリットがあります。
しかし、勘定科目を用いる時に以下の3つの注意点があることも、覚えておく必要があります。
● 勘定科目は企業の裁量で自由に決められる
● 1度決めた勘定科目は継続的に利用する
● 科目を「報告用」と「仕訳用」に分類する
これからそれぞれ解説していくので、勘定科目を適切に使用するために確認していきましょう。
勘定科目は企業の裁量で自由に決められる
会計処理を行う上で「経理自由の原則」というルールがあり、企業の裁量で勘定科目を自由に決められることになっています。
したがって、各企業で業種に合った最適な勘定科目を使用できます。
ただし、自由といっても勘定科目は外部にも公表される損益計算書などの決算書類に記載されるため、社内だけでなく社外の人が見ても分かるような勘定科目にするのが大切です。
1度決めた勘定科目は継続的に利用する
会計の考え方で「継続性の原則」というルールがあり、1度決めた勘定科目は継続的に利用する必要があります。
もし、都合が悪くなったからといって勘定科目を毎期変更してしまうと、過年度の決算資料と比較ができなくなり、経営状況を正しく把握できません。
効率的に正しく損益計算書を分析するためにも、勘定科目は変更せずに使用するように注意しましょう。
科目を「報告用」と「仕訳用」に分類する
勘定科目を「報告用」と「仕訳用」に分類して利用する点にも、注意しましょう。
勘定科目を用いた損益計算書などの決算書類は、社内だけでなく社外の人も確認するため、会計原則に沿った一般的な表現で記載します。
例えば、仕訳時の勘定科目は売上でも、外部に報告する損益計算書には売上高と記載し、社内で仕入の勘定科目を使っていた場合は、損益計算書には売上原価と表示します。
勘定科目を「報告用」と「仕訳用」に分類して、適切に使用していきましょう。
まとめ
この記事では、損益計算書の勘定科目一覧を項目ごとに解説しました。
一見すると似た名称の勘定科目があるため、本記事を参考にしていただき、各勘定科目の理解を深めましょう。
また、勘定科目を用いる理由は下記の4つです。
● 仕訳をして決算書類を作成するため
● みんなが同じ方法で帳簿作成と分析を可能にするため
● お金の流れを把握し経営改善するため
● 税金の計算をするため
勘定科目を用いると、決算書類を作成でき、お金の流れを把握できるなど多くのメリットがあります。
一方、勘定科目を用いる時の3つの注意点は、下記の通りです。
● 勘定科目は企業の裁量で自由に決められる
● 1度決めた勘定科目は継続的に利用する
● 科目を「報告用」と「仕訳用」に分類する
上記3つの注意点を意識して適切に勘定科目を使い、損益計算書の分析を正しく行っていきましょう。