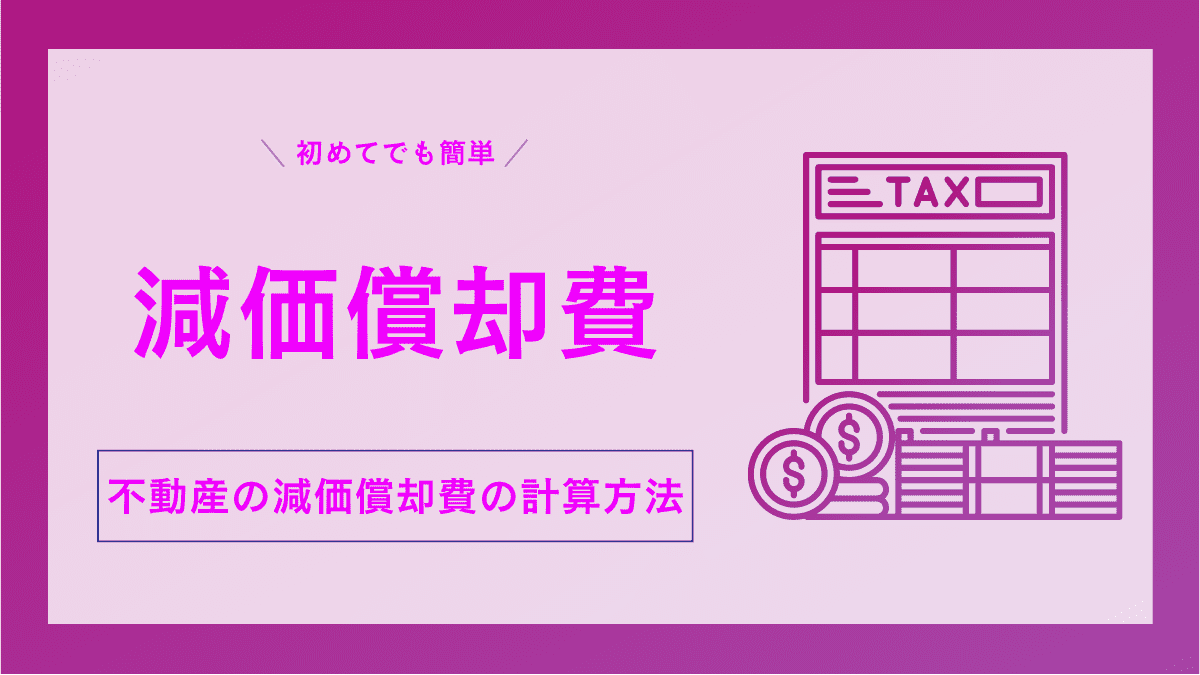不動産の減価償却費を計算する際には、使用用途や新築・中古の区分により、計算方法が異なります。
しかし、不動産の減価償却のルールを知らずに悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では不動産の減価償却の計算方法について詳しく解説していきます。
さらに不動産を減価償却する際の耐用年数の考え方や節税効果についても解説しますので、不動産の減価償却についてお悩みの人はぜひ最後までお読みください。
不動産の減価償却と3つのポイント
不動産の減価償却を考えるときに大切なポイントとして、下記の3つがあります。
・不動産の減価償却が必要な場面
・土地は減価償却できない
・税務上の耐用年数が決まっている
それぞれ解説しますので、理解を深めていきましょう。
不動産の減価償却が必要な場面
不動産の減価償却が必要な場面は主に下記の2つです。それぞれ解説します。
・賃貸収入がある場合
・売却する場合
1.賃貸収入がある場合
マンションやアパートなどの不動産経営による賃貸収入は、不動産所得として確定申告を行うことで、所得税がかかることになります。
ただし、賃貸収入を得るためにかかった修繕費や保険料などの費用と同様に、減価償却費も経費として差し引くことが可能です。
減価償却費は現金が出ていかない支出ですが経費になるため、減価償却費を計上することで節税効果を受けましょう。
2.売却する場合
不動産を売却した場合に得た利益を譲渡所得といい、所得税と住民税がかかります。
譲渡所得の計算式は下記の通りです。
譲渡所得=譲渡して得た金額(収入金額)ー(取得費ー減価償却費)ー譲渡費用
取得費は、不動産の取得価額と購入した際にかかった付随費用のことで、譲渡費用は売却するためにかかった仲介手数料や立退料などの費用のことを指します。
ポイントは、取得費から売却するまでに計上した減価償却費を差し引けることです。
取得費や譲渡費用が大きければ、譲渡所得が減り節税になりますが、減価償却費が大きいと取得費が減るため、譲渡所得が大きくなり節税効果が小さくなってしまうことに注意が必要です。
土地は減価償却できない
建物は減価償却できますが、土地は減価償却できません。
なぜなら、土地は会計上では価値の下がらないものと考えられているためです。
建物と土地は同じ不動産ですが、減価償却の考え方が異なることを覚えておきましょう。
税務上の耐用年数が決まっている
不動産を減価償却するためには費用を分割する期間の耐用年数が必要ですが、税務上の耐用年数は税法により決められています。
税法により決められた建物の構造・用途ごとの耐用年数を用いて、減価償却を行うことを覚えておきましょう。
不動産の耐用年数と考え方
不動産の減価償却を考える上で大切な要素が、耐用年数です。
不動産の取得価額を耐用年数にもとづいて分割して費用化したものが、減価償却費になります。
また、耐用年数には「法定耐用年数」「物理的耐用年数」「経済的耐用年数」の3種類があり、それぞれの定義は下記の通りです。
・法定耐用年数:不動産の構造や用途などにより、税法で決められた年数。一般的に減価償却を行う際に使用される。
・物理的耐用年数:建物の構造や資材などが劣化して、物理的に壊れてしまうまでの年数。
・経済的耐用年数:不動産の利用状況や用途などから総合的に判断された、不動産の価値が続く年数。
上記3つのうち、減価償却を行う際は法定耐用年数が使われることが一般的です。
そこで、ここでは建物と建物付属の法定耐用年数を解説していきます。
建物の構造別耐用年数
税法により決められた建物の法定耐用年数は、構造・用途ごとに異なります。
事務所用の建物の主な耐用年数を、例として下記に挙げます。
| 構造・用途 | 耐用年数 |
| 木造・合成樹脂造のもの | 24年 |
| 木骨モルタル造のもの | 22年 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造・ 鉄筋コンクリート造のもの | 50年 |
| れんが造・石造・ブロック造のもの | 41年 |
出典:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」
事務所用と区分される建物でも、構造により大きく耐用年数が異なることを覚えておきましょう。
建物附属設備の耐用年数
建物付属設備は、建物に付属して機能し、建物の価値を高める設備のことで、例えばアーケードや電気設備などが該当します。
建物付属設備の耐用年数は、下記の通りです。
| 区分 | 構造・用途 | 耐用年数 |
| アーケード・日よけ設備 | 主として金属製のもの | 15年 |
| その他のもの | 8年 | |
| 店用簡易装備 | ー | 3年 |
| 電気設備(照明設備を含む) | 蓄電池電源設備 | 6年 |
| その他のもの | 15年 | |
| 給排水・衛生設備・ガス設備 | ー | 15年 |
不動産の減価償却費の計算方法
ここでは、不動産の減価償却費の計算方法について、下記の3つの項目を解説していきます。
・不動産の減価償却費計算に必要な項目
・定額法
・定率法
不動産の減価償却費計算に必要な項目
不動産の減価償却費を計算するためには、取得費・建物と土地の割合・耐用年数・償却率について知っておく必要があります。
それぞれの意味は下記の通りなので、確認して理解していきましょう。
- 取得費:建物を取得したときにかかった金額のことで、価値が下がった金額の減価償却費を差し引いて求めます。
- 建物と土地の割合:減価償却を行う建物の取得費を知るために、建物と土地の割合を把握する必要があります。売買契約書などから把握するのが一般的ですが、記載がなければ固定資産税評価額などを参考に算出を行います。
- 耐用年数:前の章で解説した通り、税法で決められた法定耐用年数を使うのが一般的です。国税庁のホームページをご覧になれば、建物と建物付属設備の耐用年数を確認できます。
- 償却率:耐用年数ごとに定められ、減価償却費を決める割合のことです。例えば定額法の場合は、不動産の取得価額に償却率をかけることで減価償却費を求めます。
定額法
定額法は、毎年均等に減価償却費を計上する計算方法です。
計算式は下記の通りです。
減価償却費=不動産の取得価額×償却率(定額法)
なお、建物・建物付属設備は、基本的に定額法で減価償却を行うことになっています。
定率法
定率法は、初年度に多額の減価償却費を計上し、年が経つごとに減価償却費が減っていく計算方法です。
計算式は下記の通りです。
減価償却費=不動産の帳簿価額(未償却残高)×償却率(定率法)
なお、平成28年度の税制改正で、建物や建物付属設備の減価償却は定額法で行うことになりました。
したがって、不動産の減価償却を考える際は定額法の計算方法を参考にし、機械装置や車両運搬具などの不動産以外の固定資産の減価償却を考えるときに定率法を参考にしてください。
不動産の使用用途で異なる減価償却費の計算方法
不動産を所有していて賃貸収入がある場合や売却する場合は、減価償却が必要になります。
そこで、ここでは不動産の使用用途で異なる減価償却費の計算方法を解説します。
解説するのは、下記の3つの項目です。
・事業用不動産の減価償却費の計算方法
・居住用不動産の減価償却費の計算方法
・事業用不動産と居住用不動産の耐用年数
それぞれ解説しますので、確認していきましょう。
事業用不動産の減価償却費の計算方法
事業用不動産は、マンションやアパートなどの貸付用の建物、または倉庫や事務所などの事業用の建物など、収益を得るための不動産を指します。
事業用不動産の減価償却は、取得した年月によって計算方法が異なります。
平成19年(2007年)4月1日以降に取得し、定額法で減価償却を行う場合の計算式は下記の通りです。
減価償却費=建物の取得価額×定額法の償却率×当年の業務に使用された月数÷12
定額法の償却率は、国税庁が出している減価償却資産の償却率等表からご確認ください。
また、平成19年(2007年)3月31日以前に取得し、定額法で減価償却を行うときの計算式は下記の通りです。
減価償却費=(建物の取得価額ー残存価額)×旧定額法の償却率×当年の業務に使用された月数÷12
残存価額は建物の取得価額の10%のため、下記の計算式でも求められます。
減価償却費=建物の取得価額×0.9×旧定額法の償却率×当年の業務に使用された月数÷12
なお、「当年の業務に使用された月数÷12」の部分は、月割計算を行うためにつけてあるため、当年で減価償却費を計上する月数を当てはめて計算をしてみてください。
居住用不動産の減価償却費の計算方法
居住用不動産は、自分自身が住んでいるマンションや一戸建てなどの非事業用不動産のことです。
居住用不動産の減価償却費の計算方法は、下記の通りです。
減価償却費=建物の取得価額×0.9×償却率×経過年数
事業用不動産では月割計算を行いますが、居住用不動産は経過年数の考え方を用いて年単位で計算します。
経過年数を求める際は、6ヶ月以上で1年としてカウントし、6ヶ月未満の端数は切り捨てとなります。
例えば、経過年数が7年8ヶ月であれば「8年」、12年2ヶ月であれば「12年」です。
また、経過年数は所有期間のことで、築年数のことではない点に注意をしましょう。
事業用不動産と居住用不動産の耐用年数
事業用不動産と居住用不動産の耐用年数はそれぞれ異なり、まとめた表は下記の通りです。
| 建物の構造 | 事業用 | 居住用 | |||
| 耐用年数 | 償却率 | 耐用年数 | 償却率 | ||
| 木造 | 22年 | 0.046 | 33年 | 0.031 | |
| 木造モルタル | 20年 | 0.050 | 30年 | 0.034 | |
| (鉄骨)鉄筋コンクリート | 47年 | 0.022 | 70年 | 0.015 | |
| 金属造① | 3mm以下 | 19年 | 0.053 | 28年 | 0.036 |
| 金属造② | 3mm超4mm以下 | 27年 | 0.038 | 40年 | 0.025 |
居住用不動産(非業務用建物の償却費)の償却率は、下記からご確認ください。
出典:国税庁「No.3261 建物の取得費の計算」
なお、居住用の不動産は事業用の不動産の1.5倍の耐用年数とされており、理由は自宅の売却時に多額の税金を発生させない配慮があるためです。
すでに解説しましたが、不動産を売却するときの計算式は下記の通りです。
譲渡所得=譲渡して得た金額(収入金額)ー(取得費ー減価償却費)ー譲渡費用
居住用の不動産は、耐用年数が長いため償却率が小さく設定されています。
したがって、減価償却費も小さいため、建物の取得価額は長く残り続けることになります。
上記の計算式では、取得費から減価償却費を引くことになっていますが、減価償却費が小さければ取得費が大きく残ることでしょう。
そして、取得費が大きく残れば、譲渡して得た金額から大きな金額を差し引けることになるため、譲渡所得も小さく算出されます。
中古不動産の減価償却費の計算方法
不動産を取得するとき、中古不動産のケースもあることでしょう。
そこで、ここでは事業用不動産と居住用不動産がそれぞれ中古のケースについて、減価償却費の計算方法を解説していきます。
事業用不動産を購入した場合
購入した事業用不動産が中古のとき、購入したケースにより、下記の2つの計算で耐用年数を求めて減価償却を行います。
1.中古の不動産を取得時、既に全ての耐用年数を経過していた場合:法定耐用年数×20%
2.法定耐用年数の一部を経過していた場合:(法定耐用年数ー経過した年数)+(経過した年数×20%)
なお、計算結果の小数点以下は切り捨てることとし、2年未満は2年とします。
1の例は、耐用年数が24年の木造の事務所用の建物を購入したときに、既に30年経過していたケースです。
計算式は下記の通りです。
法定耐用年数(24年)×20%=4.8年
小数点以下の端数は切り捨てのため耐用年数は4年となり、定額法の償却率0.250を使用して減価償却費の計算を行います。
2の例は、耐用年数が24年の木造の事務所用の建物を購入したときに、8年経過していたケースです。
計算式は下記の通りです。
(法定耐用年数(24年)ー経過した年数(8年))+(経過した年数(8年)×20%)
=16年+1.6年=17.6年
小数点以下の端数は切り捨てのため耐用年数は17年です。
したがって、耐用年数17年の定額法の償却率0.059を用いて、減価償却を行います。
居住用不動産を購入した場合
購入した居住用(非業務用)不動産が中古のとき、新築と同様に構造ごとに決められた償却率を使用して減価償却を行います。
居住用不動産の耐用年数は、国税庁のホームページで確認できます。
居住用不動産の耐用年数と償却率は下記の通りです。
| 建物の構造 | 居住用 | ||
| 耐用年数 | 償却率 | ||
| 木造 | 33年 | 0.031 | |
| 木造モルタル | 30年 | 0.034 | |
| (鉄骨)鉄筋コンクリート | 70年 | 0.015 | |
| 金属造① | 3mm以下 | 28年 | 0.036 |
| 金属造② | 3mm超4mm以下 | 40年 | 0.025 |
例えば、(鉄骨)鉄筋コンクリート造の中古マンションを購入したとき、何年経過していても償却率0.015を使用して減価償却を行います。
不動産の減価償却の節税効果
ここまで不動産の減価償却について解説しましたが、下記の2つのケースでの節税効果を解説します。
・不動産収入の減価償却の場合
・不動産売却の減価償却の場合
不動産収入の減価償却の場合
マンションやアパートなどの不動産収入があった場合、減価償却費を経費として計上し所得から差し引くことで、節税効果を受けられます。
とくに耐用年数が短い中古の不動産であれば、減価償却費の計上が多くなるため、節税効果を大きく受けられるでしょう。
不動産売却の減価償却の場合
不動産を売却した場合、所得税を考えたときに減価償却費を多く計上していた方が節税効果を大きく受けられます。
ここでは耐用年数の異なる新築物件と中古物件を例に挙げて、比較していきましょう。
前提条件は下記の通りです。
・新築物件も中古物件も取得価額1,000万円
・耐用年数は、新築物件が30年、中古物件が10年
・10年後に800万円で売却
・住民税は考慮しない
・売却にかかる手数料はかからない
上記の条件から、状況をまとめた表は下記の通りです。
| 区分 | 耐用年数 | 償却率 | 売却時の減価償却費累計額 | 売却時の帳簿価額(未償却残高) |
| 新築 | 30年 | 0.034 | 1000万円×0.034×10年=340万円 | 660万円 |
| 中古 | 10年 | 0.100 | 1000万円×0.100×10年=1,000万円 | 1円 |
まずは、不動産を売却したときにかかる譲渡所得税について考えてみましょう。
新築物件は帳簿価額が残っているため、譲渡所得税率15%(所有期間5年超)分の99万円(660万円×15%)の節税が可能です。
一方、中古物件は償却が終わっているため、売却したときの節税効果はありません。
次に、不動産を利用しているときの節税効果を考えてみましょう。
不動産を利用しているときは、減価償却費を計上することで確定申告の際に節税効果を受けるため、効果計算では所得税率を使用します。
所得税は累進課税で、所得金額が330万円を超えると所得税率が20%になることから、譲渡所得税率の15%よりも高い税率であることが想定されます。
上記の節税効果をまとめた表は、下記の通りです。
| 区分 | ①売却時の節税金額 | ②不動産利用時の節税金額 | ①+②節税効果の合計 |
| 新築 | 99万円(660万円×15%) | 340万円×所得税率 | 340万円×所得税率+99万円 |
| 中古 | 0円 | 1,000万円×所得税率 | 1,000万円×所得税率 |
上記の表より、所得税率と譲渡所得税率の差があることから、不動産利用時の節税金額が大きいと考えられるため、中古物件の方が節税効果を大きく受けているといえるでしょう。
不動産を減価償却する際の注意点
不動産を減価償却する際は、さまざまな状況が想定されます。
そこで、ここでは不動産を減価償却する際の注意点として下記の2点を解説します。
・不動産と土地を分けて考える
・使用用途が変わった時の減価償却の計算方法
建物と土地を分けて考える
建物は減価償却ができますが土地は減価償却ができないため、取得価額などを分けて考えなければなりません。
したがって、建物と土地を一括で取得した場合は、建物と土地の取得価額を分けることが必要です。
建物と土地の取得価額が契約書に記載されていれば問題ありませんが、もし記載がなければ固定資産税評価額などを使用して、合理的な説明ができる基準で分けるようにしましょう。
使用用途が変わった時の減価償却の計算方法
同じ建物でも、使用用途が変われば耐用年数が変わります。
例えば、木造の建物で事務所用のものは耐用年数が24年、店舗用・住宅用のものは22年です。
したがって、使用用途を変えた時から、変えた使用用途の耐用年数を使用して減価償却費の計算をすることになります。
なお会計期間の途中で使用用途を変えた場合は、翌年の年初から、変えた使用用途の耐用年数で減価償却費の計算ができます。
まとめ
本記事では、不動産の減価償却費の計算方法を詳しく解説しました。
不動産の減価償却は、主に賃貸収入があるときと売却するときに必要です。
土地は減価償却できないことと、税務上の耐用年数は決まっていることも覚えておきましょう。
また、不動産の減価償却は、事業用不動産と居住用不動産の使用用途により計算方法が異なります。
事業用不動産の減価償却は、取得した年月によって計算方法が異なります。
平成19年(2007年)4月1日以降に取得した場合の計算式は、下記の通りです。
減価償却費=建物の取得価額×定額法の償却率×当年の業務に使用された月数÷12
平成19年(2007年)3月31日以前に取得した場合は、下記の計算式になります。
減価償却費=建物の取得価額×0.9×旧定額法の償却率×当年の業務に使用された月数÷12
また、居住用不動産の減価償却費の計算方法は下記の通りです。
減価償却費=建物の取得価額×0.9×償却率×経過年数
居住用不動産は、事業用不動産とは異なり、経過年数の考え方を用いて年単位で計算することに注意をしましょう。
さらに、中古不動産の減価償却費の計算方法も解説しました。
中古の事業用不動産を購入した場合は、購入したケースにより、下記の2つの計算式のどちらかで耐用年数を求めてから減価償却を行います。
・中古の不動産を取得時、既に全ての耐用年数を経過していた場合:法定耐用年数×20%
・法定耐用年数の一部を経過していた場合:(法定耐用年数ー経過した年数)+(経過した年数×20%)
一方、中古の居住用不動産を購入した場合は、新築と同様に構造ごとに決められた償却率を使用して減価償却を行います。
不動産の減価償却は、使用用途や新築・中古の区別により計算方法が異なるため、該当するケースに当てはめて減価償却を行ってください。